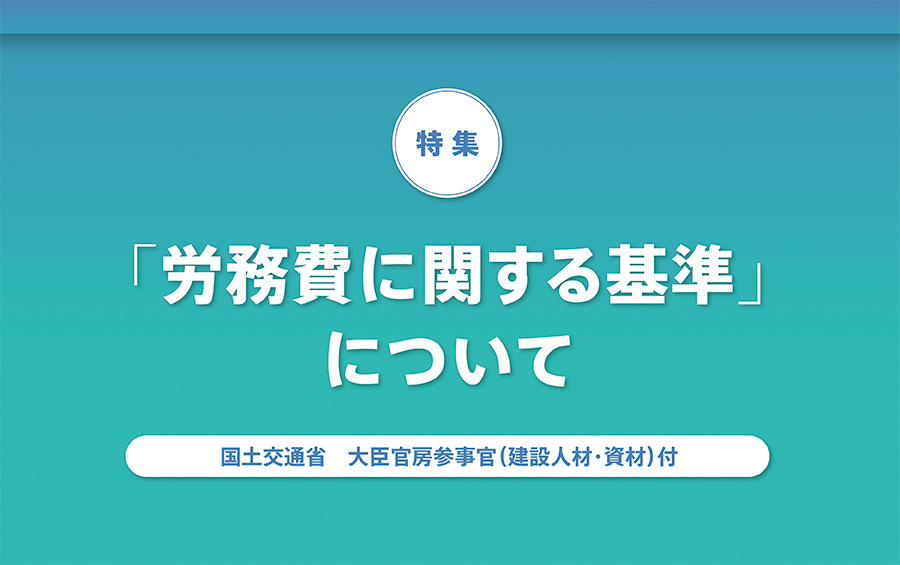特集
【鼎談】建設系専門学校の 役割と取組について

佐々木 建設業界の担い手確保・育成に関して、取り組んでいかなければいけないことや、建設業界に望むこと、その他、建設企業への要望等をお聞かせください。
山 野 担い手不足で建設業界の方々がとても忙しいのは、重々承知しています。しかしながら、建設企業は、 技術者・技能者の確保に向けて、たくさん社会貢献をしていく必要があると思います。例えば、30代の第一線で活躍している技術者・技能者の方々が出前講座などに出向いて、建設業の楽しさ、魅力、やりがいを伝えていかなければいけません。
技術者・技能者の確保に向けて、たくさん社会貢献をしていく必要があると思います。例えば、30代の第一線で活躍している技術者・技能者の方々が出前講座などに出向いて、建設業の楽しさ、魅力、やりがいを伝えていかなければいけません。

鈴 木 依然として、建設業新規入職者の離職率が高いということが問題だと思います。せっかく業界に就職したのに、「辞めても仕方がない」と考えている企業側の意識を変えていく必要があります。新卒者を育成する体制が社長からトップダウンで徹底されている企業は、離職率が低いのです。これまでやってきたやり方を変えて、企業側として「辞めさせないための取組み」を徹底する必要があります。離職させないための取り組みをぜひ実施していただきたい。建設業を廃業せざるを得ない企業を出さないためにも人を育てる意識の改革が必要だと思います。
佐々木 女性が建設業で働くことや、学び直しについてはどのようにお考えでしょうか?
鈴 木 現場のトイレがきれいなことはいいことだと思いますが、それ以上に一人の技術者、技能者として見られたいという女性の声をよく聞きます。輝いている女性は、男性と同等以上に渡り合って、活躍しています。
佐々木 建設業に就職した若者は3年で5割の方が退職されてしまうというデータもあり、その大きな原因は上司の無理解だそうです。女性を増やすためだけでなく、そもそも新規入職者を受け入れる現場づくりも、進めていかなければなりませんね。
 山 野 学び直し人材を活用するリカレント教育・訓練も国の施策として注目されています。この分野も取り組んでいく必要がありますね。
山 野 学び直し人材を活用するリカレント教育・訓練も国の施策として注目されています。この分野も取り組んでいく必要がありますね。
佐々木 様々な理由で定職についていない方も多くいますが建設業の仕事が合って、社会復帰につながったという話もあります。色々な背景を持つ方々に建設業界で仕事をしていただくことができないかと思います。
山 野 2018年8月、専門学校等において、社会人の職業に必要な能力の向上及びキャリア形成を図る機会の拡大することを目的として、「専修学校におけるキャリア形成促進プログラムの認定に関する規程」が施行されました。また同年9月に厚生労働省の専門実践教育訓練給付金の指定基準の見直しが行われ、キャリア形成促進プログラムとして認定された課程のうち一定の基準を満たすものについて、専門実践教育訓練給付金の支給対象となりました。最近は正社員として雇用した人を、入社後に専門学校に送り込むという取組をしている企業もあります。
鈴 木 本校の夜間部に採用者全員を入学させる会社さんも出てきました。そのように専門学校を活用していただけるのは有意義なことだと考えます。土木系の中でも、特に測量分野は人材が不足しています。そこで、普通科や農業系の高校を卒業した人を採用し、専門学校で教育訓練を受けさせ、技術者として育成するという取組もスタートしています。産官学で連携し、具体的に実りのあることをやっていきたいですね。そのために専門学校が貢献できることはたくさんあると考えます。
佐々木 私どもも、各方面に働きかけつつ、できるところから取り組んでいきたいと思います。今後ともぜひご協力をお願いします。本日はありがとうございました。

【冊子PDFはこちら】