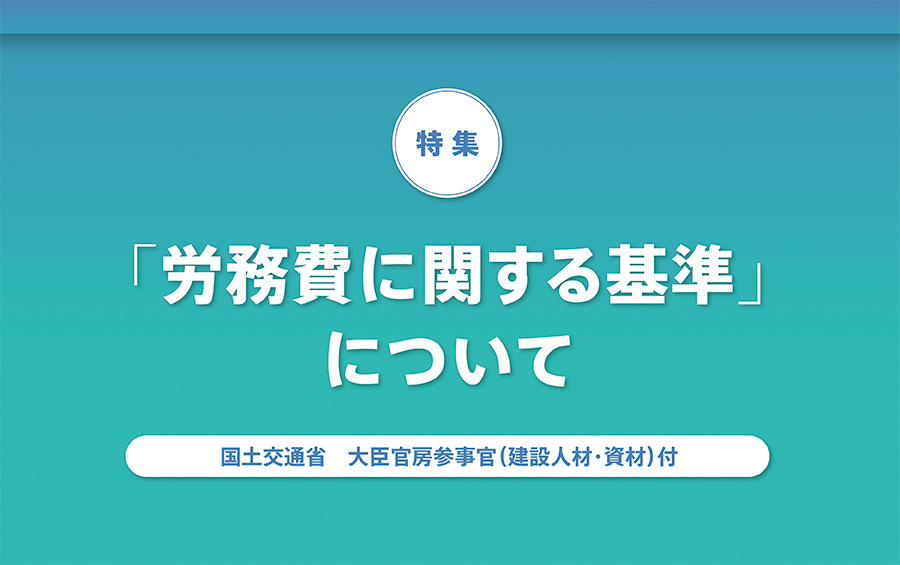特集
地域建設業に・効く・i-Construction 調査結果について
意見交換会
29年度調査業務報告書における論点と課題
各社の実体験から生まれたノウハウに注目

| 司会進行 | 新井 恭子氏 (京都サンダー株式会社代表取締役) |
| コーディネーター | 建山 和由氏 (立命館大学教授) |
| 高田 守康氏 (日本マルチメディア・イクイップメント(株)代表取締役) |
各社の事例発表を受けて、出席者全員による意見交換会が行われました。新井氏の司会進行のもと、建山、高田の両氏がコーディネーター役を務め、それぞれの現場で業務改革に取り組む方々の、実体験に基づいた意見に熱心に耳を傾けていました。
■オペレーターではなくクリエイターを育てる教育の必要性
| 建山氏 | ICTによるi-Constructionにとどまらないそれぞれの企業の独自のやり方で、生産性向上に向けたより様々な取り組みが生まれている。その上で、リーダーが実現する強い意志と、豊かな想像力を発揮できる人材育成が不可欠である。 |
| 小原文男氏 (株)コイシ |
いつも CAD オペレーターに対し、『言われたことだけを描くのはダメだ』と言っている。図面の意味を理解しながら作業できる知識や能力が必要不可欠だ。自分の目で図面を理解できるようになれば、やがては仕事を改革できるクリエイターとして成長してくれると期待している。 |
■さまざまな体験が新しい発想や成長につながる
| 高田氏 | デジタル技術の進化によって、仕事の技能の再構築が必要な時代になってきている。一度勉強して終わりではなく、リカレント教育のように組織として繰り返しフォローアップしていける仕組みづくりが必要だ。 |
| 建山氏 | 現在の測量用レーザースキャナーは、近距離の測定精度が低くなる特性があるが、その欠点を解決したすごいスキャナーが出るのも、そう遠い話ではない。常に技術の進化にアンテナを張って、新しく出てきたものを柔軟に取り入れるために、勉強会やコンソーシアムなどを作るべきだ。生産性向上のための安全対策も重要だ。ICTを使うことで、重大な事故を減らせる期待ができる。 |
| 菅原直樹氏 (株)菅原設備 |
ゼネコンや厚生労働省が保有している事故事例データをオープン化して標準の作業手順と付け合わせれば、事故発生のパターンが“見える化” できるはず。 |

また出席者からは、AIやIoTを応用して、入場時の作業者をカメラで撮って安全をチェックするシステムや、HoloLensなどの装着型デバイスを使ったVR/ARによる3Dシミュレーション体験など有効ではないかと意見があった。
■新たな流れ、異業種との連携による新発想の創出
最後に建山氏から、「異業種からも技術的な面から協力したいという希望がある。そうした人たちと情報共有していくことも大事になってくる。意識のある人たちが集まって、次の新しい流れを創る努力が必要だ。」と述べ、意見交換会を締めくくりました。
報告会に参加してみて…
「ICT・人材育成等、様々な取組による企業収益向上に期待!」

一般財団法人 建設業振興基金理事長
内田 俊一
※報告会開催当時。本年6月29日より特別相談役に就任
私は、最初にi-Constructionの構想が国土交通省から示された時、ICTを活用して生産性を向上するのは良いが、それによって建設産業各社の利益がどうなるのか見えない点に少しの懸念を感じていました。建設産業の供給力を維持するのは最重要課題ですが、企業経営の観点からは、その取り組みからどれだけの収益を実現できるかが重要です。
その意味で本日の発表には、利益につながる生産性向上というまさに期待通りの取り組みが生まれてきていると感じました。ぜひ今後も、地域の建設産業が確実に収益を上げられるよう、各社それぞれの強みをつくりだし、磨きをかけていただきたい。私たちもこの難しい課題に挑戦する皆さんに少しでも貢献できるよう、これまでの成果を踏まえて取り組んでいきたいと思います。
【冊子PDFはこちら】