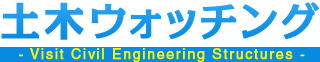かわいい土木
父のようにまちを守る「尼ロック」

Photo・Text : フリーライター 三上 美絵
大成建設広報部勤務を経てフリーライターとなる。「日経コンストラクション」(日経BP社)や土木学会誌などの建設系雑誌を中心に記事を執筆。
広報研修講師、社内報アワード審査員。著書『土木技術者になるには』(ぺりかん社)、本連載をまとめた『かわいい土木 見つけ旅』(技術評論社)
「尼ロック」の愛称を持つ尼崎閘門。日本一の規模を誇る“船のエレベーター”にもかかわらず、その存在は地元でもあまり知られていないらしい。ところがこの閘門、ホームコメディ映画では「ふだんはぐうたらだが、いざというときには家族を守る父親像」のシンボルになった。いったいどういうことか。尼崎の歴史をたどると、その理由が見えてくる。
昨年(2024年)春に公開された映画「あまろっく」をご存知だろうか。主人公一家がスワンボートに乗って尼崎閘門、愛称「尼ロック」を通過する冒頭シーンが印象的だ。
江口のりこさん演じる主人公は子ども時代、この体験をレポートにまとめて学校で発表するが、クラスメイトは誰も尼ロックの存在を知らず、まったくウケない。
私が現地を訪れたときも、タクシーの運転手さんは場所が分からず、「最近、映画になったアレです」と説明してようやく了解してもらったものの、「なんでそんなとこ行きたいん?」とけげんな顔をされてしまった。
 ▲愛称「尼ロック」の碑があった。後方左に見えるのが閘門監視室。
▲愛称「尼ロック」の碑があった。後方左に見えるのが閘門監視室。
水位差を解消して船を通すだけじゃない、大切な役割
「閘門」については、過去にも岡山県の倉安川吉井水門(かわいい土木第12回しんこうweb ▶︎ https://www.shinko-web.jp/series/1767/ )と埼玉県の見沼通船堀(かわいい土木第39回しんこうweb ▶︎ https://www.shinko-web.jp/series/8252/ )を紹介したことがある。よく「船のエレベーター」と表現されるように、二つの川や運河の水位差を調節することで、船が通行できるようにする施設だ。壁で囲まれたプールのような「閘室」の片方の扉から船を入れ、扉を閉めて給排水装置によって水位を変えたら、もう片方の扉を開けて船を出す。これが一連の動作だ。
尼ロックは2基の閘門が並ぶ「双閘」で、長さ90m、幅17mの大きさは、日本では最大だという。南堀運河沿いの遊歩道を歩いて第2閘門へ着いたとき、ちょうど漁船が出ていこうとしていた(下の写真)。扇型の扉がゆっくり閉まる様子を見られたのはラッキーだ。
 ▲第2閘門から船が大阪湾へ出て行く。
▲第2閘門から船が大阪湾へ出て行く。
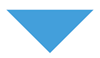
 ▲前扉は開き、写っていないが後扉は閉じた状態だ。
▲前扉は開き、写っていないが後扉は閉じた状態だ。
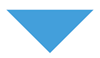
 ▲船が去り、前扉が閉じ始める。
▲船が去り、前扉が閉じ始める。
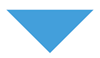
 ▲完全に閉じるまで、5分ぐらいか。
▲完全に閉じるまで、5分ぐらいか。
船を通行させることに加えて、尼ロックにはもう一つ重要な役割がある。市街地を水害から守ることだ。大正時代以降、工業地帯として栄えた尼崎は、地下水の汲み上げによる地盤沈下が進み、台風や高潮の被害をひんぱんに受けるようになった。その対策として1955年(昭和30年)に完成したのが、防潮堤と尼ロックだ。高潮のときには門扉をぴったり閉じて、海水の逆流を防ぐ。
 ▲大阪湾側から第2閘門を見る。緑色の部分が「セクターゲート」と呼ばれる門扉。隣に第1閘門があるが、陸側からは見ることができない。第1閘門から第2閘門へは道路を大回りすることになるので、見に行くなら直接第2閘門を目指そう。
▲大阪湾側から第2閘門を見る。緑色の部分が「セクターゲート」と呼ばれる門扉。隣に第1閘門があるが、陸側からは見ることができない。第1閘門から第2閘門へは道路を大回りすることになるので、見に行くなら直接第2閘門を目指そう。
 ▲濃い青線の線が防潮ライン。尼ロックもその一部だ。
▲濃い青線の線が防潮ライン。尼ロックもその一部だ。
 ▲2基の閘門が並ぶ。閘門監視室では24時間、人が目視で船を確認し、閘門の開閉をしている。
▲2基の閘門が並ぶ。閘門監視室では24時間、人が目視で船を確認し、閘門の開閉をしている。
映画「あまろっく」では、笑福亭鶴瓶さん演じる父親がTVの前にだらしなく寝そべり、腰のあたりをボリボリと掻きながら「お父ちゃんはわが家の尼ロックや」とうそぶいていた。
ふだん目立たなくても、いざというときにどっしりまちを守る姿は、たしかに似ているかもしれない。
●アクセス
阪神本線「尼崎センタープール前駅」から「南堀運河沿い遊歩道入口」まで車で約7分。遊歩道を10分ほど歩くと第2閘門の脇まで行くことができる。
【冊子PDFはこちら】