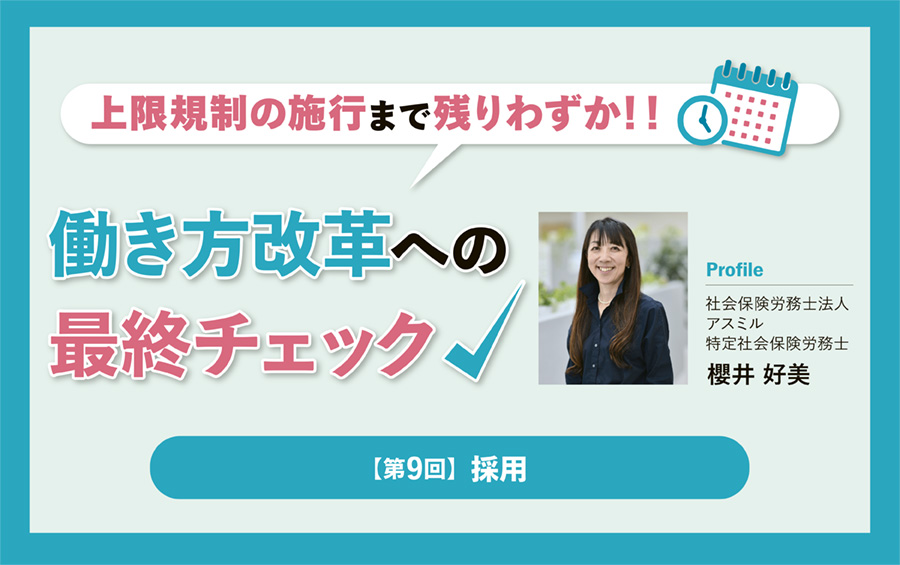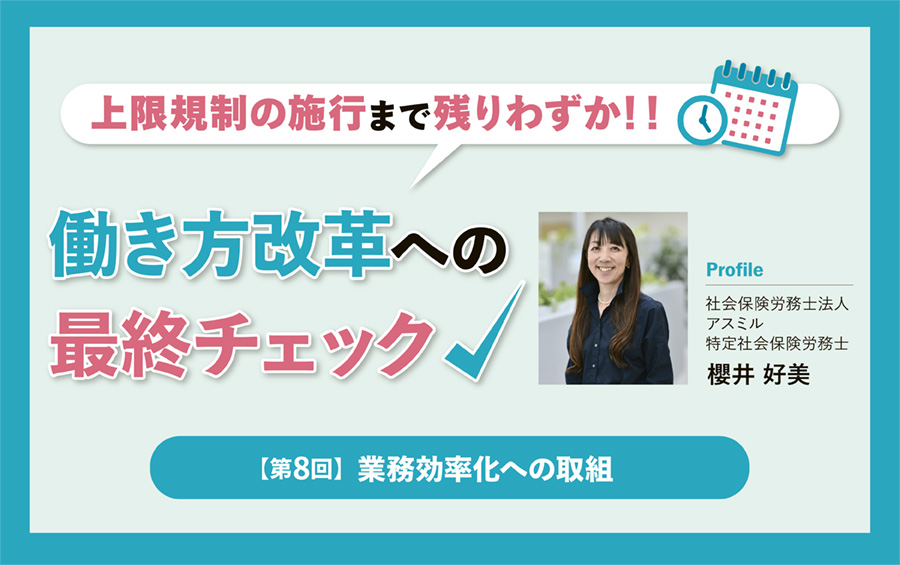働き方改革への最終チェック
定着率向上への取組
取組事例
きっかけ きっかけは「管理部門」
以前は、他の工務店と同じように休日数も同業並み、そして大工も外注が中心でした。しかし、管理部門を強化することにより、会社の体制づくりに力をいれていくようになりました。
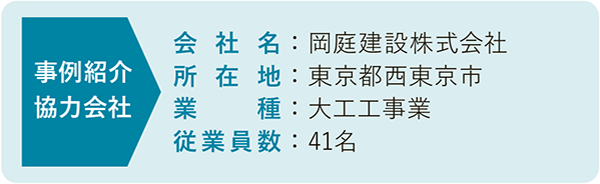

大工の採用
工務店であるため大工の育成は必須です。高校生にはインターンシップ制度をとっており、高校2年生の時に3日間必ず現場をみてもらいます。そこで興味を持った子供たちが応募をしてくれるためミスマッチを防ぐことができます。建設業の仕事は屋内作業だけではなく、暑さの厳しい中でも作業をしなくてはならないため、しっかりと現場をみてもらうことが重要だと考えています。
新入社員の育成
中小零細企業にとって、社内で1から人を育てるのは大変です。弊社では、新人大工は東京大工塾(tokyo-daiku-jyuku.com)で教育をし、基本的なことを習得してもらいます。教育機関ですべてが完結するわけではありませんが、基本的なことを理解してから現場にでることで、少しでも不安を解消することができ、先輩も教える手間が省けるようになりました。その他にも、1年目、2年目の社員については、4ケ月ごとに定期面談をし、仕事での悩み、困っていることをきくことで社員の離職を防いでいます。また入社3年生を新人のメンターにつけることで、日常の些細な困りごとを相談できるようにしています。
フューチャーミーティングの実施
職場では仕事の話しかすることはできませんが、フューチャーミーティングでは自分がやりたいこと、会社にしてほしいこと等を吐き出す場を作っています。個々人の仕事への価値観も多様化する中で、お互いを理解すること、その中で会社は何ができるかを検討できる場になっています。

山林見学会の実施
木造の家を建てているため、実際にその木材はどこからきているのか?木材の伐採から加工までの見学会を実施しました。加工場には伐採された木材が並び、そこで「岡庭建設〇〇邸様」といった木材を目にすることにより、自分たちの仕事の流れが確認出来、お客様にも自信をもって対応もできるようになりました。仕事の楽しさを感じてもらえるきっかけになっています。

コミュニケーションの機会づくり
社員のコミュニケーションを円滑にするために、曜日を決め、夕方からモデルハウスでアルコールが飲めるような環境づくりをしました。まだ利用しているのは一部ですが、仕事とは関係のない環境をつくることで、普段相談できないようなことを気軽に相談できる場にしたいと思っています。
今後の課題
現場においてはCCUS(建設キャリアアップシステム)の導入、社内ではいくつかのシステムを導入してきました。それぞれ稼働はしていますが、さらに今のシステムを連携し効率化をはかることで、従業員の人達が今まで以上に自分の業務に集中できるよう環境を作っていきたいと思っています。
【冊子PDFはこちら】