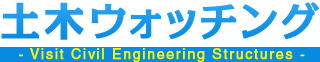かわいい土木
変わりながら変わらない「流れ橋」

Photo・Text : フリーライター 三上 美絵
大成建設広報部勤務を経てフリーライターとなる。「日経コンストラクション」(日経BP社)や土木学会誌などの建設系雑誌を中心に記事を執筆。
広報研修講師、社内報アワード審査員。著書『土木技術者になるには』(ぺりかん社)、本連載をまとめた『かわいい土木 見つけ旅』(技術評論社)
洪水に抗わず、ばらばらになって流されてしまう「流れ橋」。岩手県の住田町にある松日橋は、古くから住民たちの手で架け直され、受け継がれてきた。洪水で流されるたびに、微妙に姿を変えながらも、ずっと変わらずそこに存在する橋の魅力を追った。
岩手県・住田町の下有住地区。童話を連想させる「ありす」というかわいらしい名前を持ったこの地区に、住民たちの手で古くから何度も架け直されてきた橋がある。それが気仙川に架かる「松日橋」だ。
自然の力を受け流す
日本らしい知恵
松日橋の特徴は、「流れ橋」であること。川が増水すると、橋桁が浮き上がって橋脚が外れ、ばらばらになって流されてしまう仕組みだ。「流されてしまう」というより、あえて流れるようにつくってある。もし川の中にそのまま橋が残っていれば、流木などが引っかかってダムのように水をせき止め、やがて堤防が決壊して災害を起こしかねないからだ。
流されるといっても、松日橋の場合、部材をワイヤーロープで連結し、土手の木に結びつけてあるので、流失してしまうことはめったにない。天候が回復して水位が下がったら、部材を回収して再び橋を架け直せばよく、実に合理的だ。
松日橋は、「ザマザ」と呼ぶ橋脚の上に、「橋板(橋桁)」を載せるシンプルな構成でできている。ザマザは、クルミなどの樹木のY字型に枝分かれした部分を伐り出し、逆さまにして用いる。具体的には、短い横梁の両端にホゾ穴をあけ、ザマザのホゾを差し込んでハの字に開く。こうしてできた脚立のような形の橋脚を4基、川の中に設置し、その上に橋板を載せる。橋板の重みと、ザマザにかかる水圧によって橋は安定し、普段の水量では流されることはない。
自然の力に無理に抗わず、受け流すことで大きな被害を回避する。その思想は、とても日本的に感じられる。
 ▲地域の人たちによる橋架け作業の様子。胴付き長靴姿で川へ入り、倒れたり、流されたりしたザマザを組み直し、位置を調整する
▲地域の人たちによる橋架け作業の様子。胴付き長靴姿で川へ入り、倒れたり、流されたりしたザマザを組み直し、位置を調整する
 ▲二股になった太い枝から作るザマザ。漢字では「叉股」と書く。「サマタ」が「ザマザ」に転訛したのだろうか
▲二股になった太い枝から作るザマザ。漢字では「叉股」と書く。「サマタ」が「ザマザ」に転訛したのだろうか
流された現場と
橋の架け直しを見学
私が松日橋を訪れたのは、2025年4月。土木学会の2024年度会長プロジェクトの一つである「仕事の風景探訪プロジェクト」の事例紹介の取材のためだった。日程が決まり、現地でこのドボかわいい橋に対面するのをとても楽しみにしていた。ところが、取材日の1週間前に大雨が降り、「橋が流れてしまった」という連絡が!
「流れ橋」なのだから、当然と言えば当然。きちんと機能を果たしたわけだが、残念な気持ちは否めない。松日橋を管理する松日橋受益者組合の皆さんが、そんな取材陣の気持ちを汲んで、当日にザマザを伐り出す作業を実施してくださることになった。
流れ橋を構成する部材をつくる工程を見られる機会はめったにない。大喜びで現地へ向かったのだが、なんと当日、さらに嬉しいことが起こった。川の水量が落ち着いてきたことから、急きょ橋架け作業が行われることになったのだ。本当に、地元の皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。橋架けの様子は、土木学会の公式noteで紹介させていただいたので、ぜひご覧いただきたい。
仕事の風景探訪|自分たちで架け直す日常生活の橋。「流れ橋」をめぐる土木の原風景
 ▲でき上がった松日橋は、遠目には、昆虫のナナフシみたいでドボかわいい。橋の架け方は体験を通して地元の人々に代々受け継がれてきた。
▲でき上がった松日橋は、遠目には、昆虫のナナフシみたいでドボかわいい。橋の架け方は体験を通して地元の人々に代々受け継がれてきた。
橋架けの機会が頻繁にあるからこそ、技術が失われずに継承されているのだろう
 ▲歩いて渡ってみたら、ぐらつくこともなく、水面が近くて楽しかった
▲歩いて渡ってみたら、ぐらつくこともなく、水面が近くて楽しかった
 ▲4月の大雨で流されてしまった松日橋。
▲4月の大雨で流されてしまった松日橋。
水に浸からないところは残った
生まれ変わりながら
同じ橋として存在し続ける
松日橋がいつからあるのか、正確には分からない。遅くとも江戸時代中期には、気仙川に面した松日集落と対岸の中山集落の間で、互いの田畑などへの行き来のために橋が架けられていたと見られる。
今では上流側・下流側とも車で1〜2分のところに道路橋があるので、松日橋がなくても生活には困らないという。それでも、橋が流されればまた、声を掛け合って架け直す。義務でも当番制でもなく、作業の日に、出られる人が出る。7〜8人集まれば、ザマザを組み直し、橋板を載せて橋架けが完了。胴付き長靴を履き、川の中に入っての作業は重労働だが、地域をつなぐ絆にもなっている。
松日橋には図面はない。増水で川底の地形も変わる。架け直すつど、同じにはならない。それでも、「松日橋」としてあり続ける。この橋の魅力は、無常の中の連続性、変化を内包した不変性にある。新しくて古い松日橋の素朴で簡素なフォルムが、周辺の里山に映えて美しかった。
●アクセス
東北新幹線水沢江刺駅から車で約50分。陸前高田市内や大船渡市内からは車で約30分
【冊子PDFはこちら】