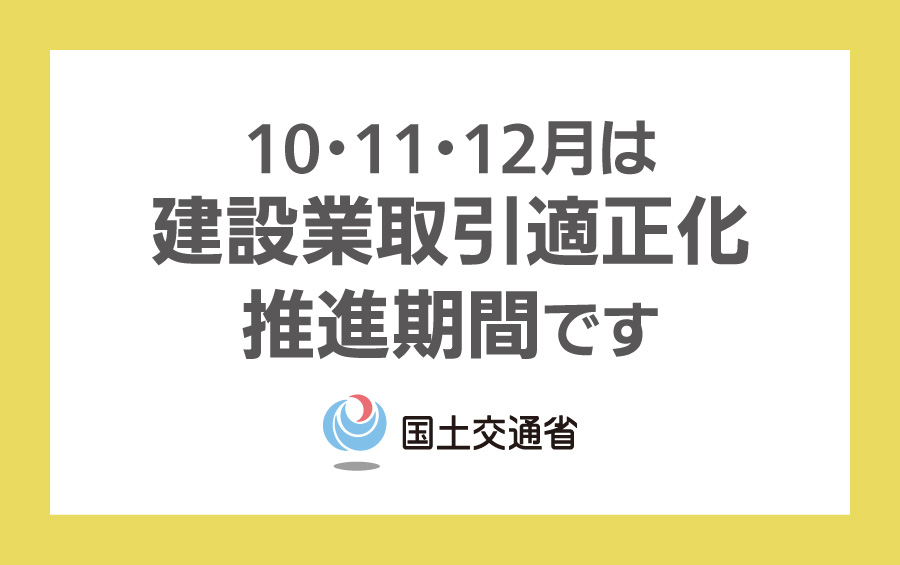インフォメーション
令和7年度「作文コンクール」受賞作品が決定!
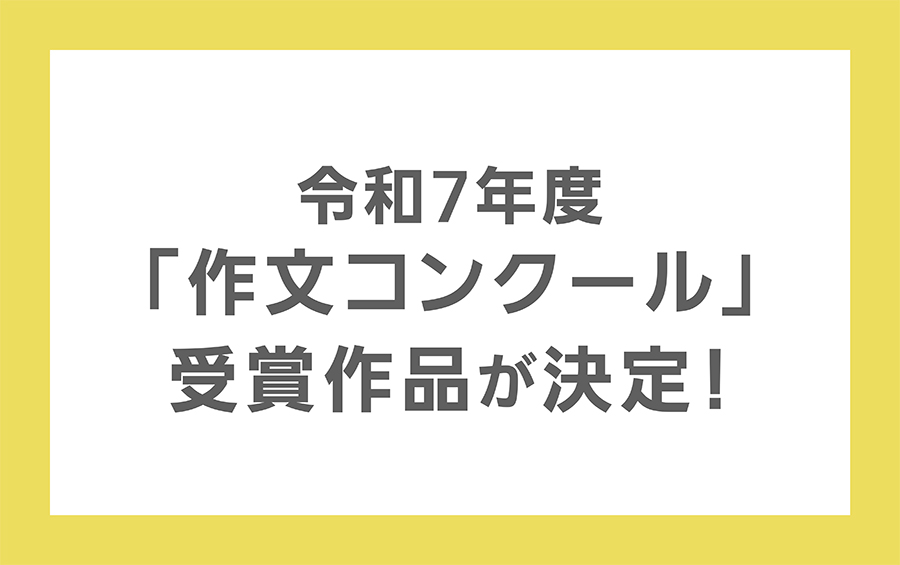
国土交通省と建設産業人材確保・育成推進協議会では、高校生の方と建設産業で働く方を対象とする作文コンクールを実施し、優秀な作品を表彰しています。今回は、国土交通大臣賞に選ばれた3作品をご紹介します。

高校生の作文コンクール 国土交通大臣賞 受賞作品
人を笑顔にする職業

金沢市立工業高等学校 土木科 2年
荒木 悠迅 さん
| 受賞者へインタビュー |
|
■Q1 受賞された感想を教えてください。 ■Q2 なぜ工業高校に進学しましたか? 建設系の勉強をしようとおもったきっかけ 等 ■Q3 学校ではどのような勉強をしていますか? ■Q4 将来の夢を教えてください。 |
自分たちが毎日使う、よく通るその道路はどのようにしてできているか知っていますか。私は毎日使う、また毎日通るこの道路について深く考えたことなんてありませんでした。しかし、2024年1月1日に起こった能登半島地震により、今までは普通に使っていた道路が寸断や崩落で使えなくなりました。そして移動するのにも今まではすぐに到着する場所でも倍以上の時間がかかり、道路が使えなくなることがどれだけ大変なことか気づかされました。そこから普段当たり前だった道路に興味を持ち、自分は工業高校に入学しました。私は工業高校に入学する前までは道路工事作業員が街で道路を直しているのを見かけるため、この方たちが道路を作っていると思っていました。ですが、この方たちだけでできているのではなく測量士の方などたくさんの人が関わっていることを知りました。また、このことにより建設産業について興味を持ちました。私の最初の建設産業の印象は「力仕事できつそう」、「自分にはできなさそう」、などといったあまり良い印象ではありませんでした。ですが工業高校に進学し、工業や建設産業について学ぶにつれてとてもやりがいのある職業だと印象が180度変わりました。
建設業は、建物を建てるのにも、道路を作るのにも欠かせない職業です。またすべての人が使い生活に欠かせないものを作る仕事です。そしてその作ったものを地図に残すことができる職業であり、今後もなくなることのない必要不可欠な職業だと私は考えています。また、人を笑顔にできる職業だと私は考えています。このように考える理由は、能登半島地震により私の祖母の家が傾き赤色の札が張られ、その家には住むのが危険と判断されたときのことでした。その札を見た祖母はとても悲しんでいました。そこで、「もうこの家には住めないのか」と泣き崩れる祖母を見ました。私は初めて祖母のこんな姿を見ました。そして月日がたち建設産業の技術により、家を直せると祖母が聞いたときとても笑顔になっているのを見ました。建設産業はあれだけ泣き崩れていた人をこんなにも笑顔にすることのできるとても素敵でかっこいい職業だなとそのとき思いました。そして私はこんな建設産業にあこがれを抱きました。私は今後建設産業界の一員となり、これからの社会を築ける立派な人になり、人を笑顔にしたいなと考えています。また私の故郷である石川県を素敵な町や社会にし、震災のあった能登を建設産業の力や魅力で地震の起こる前のような活気のある素敵な街にできるように頑張りたいです。またこれからの建設産業の発展のためにいろいろな人に建設産業の魅力を伝えていきたいなと思います。
高校生の作文コンクール 国土交通大臣賞 受賞作品
あの神社からはじまったこと

徳島県立阿南光高等学校 都市環境システム科 2年
四宮 渚咲 さん
| 受賞者へインタビュー |
|
■Q1 受賞された感想を教えてください。 ■Q2 なぜ工業高校に進学しましたか? 建設系の勉強をしようとおもったきっかけ 等 ■Q3 学校ではどのような勉強をしていますか? ■Q4 将来の夢を教えてください。 |
幼い頃、母の手に引かれて、山あいの神社を訪れた記憶がある。苔むした石畳に二つの足音を落とすたび、風の音、木々のさざめき、遥か遠くからは、ウグイスの声も聞こえてくる。かえって際立つ静けさは、まるで時さえも歩みを緩めたようで、私はただ、その空間に母の体温と春の訪れだけを感じていた。
境内の奥深くには、社が静かにたたずんでいる。風雨に洗われた細かなひびも、穏やかな色合いに変化した木の表面も、人々が長い間、大切に見守ってきたという証のように感じられ、私の幼い目に強く焼き付けられた。同時にその光景は、「どうして、あの社は長い年月を経てもなお、美しくそこにあり続けられるのだろう」という小さな問いを、心に灯した。
高校生となった私は、徳島県西部に残る「うだつの町並み」を訪れた。連なる瓦屋根や木造の格子戸、隣屋の間の「うだつ」細い路地。一本の道に映るのは、歴史の重みだけではなく、当時の人々の暮らしをうかがうことのできる、穏やかな日常の風景だった。さらに、戸ごとの家屋には、陽の入り方や風の通り道、災害から人々を守る工夫が施されていることに気づいたとき、幼い日に感じたあの問いの答えに少し触れられたような気がした。「建てる」ということは、単に形を作ることだけではない。暮らしを支え、命を守り、未来と地続きである「今」を築く行いである。そしてその本質は、昔も今も、何一つ変わっていないのだと。
今、私は高校の授業で、建設の現場を支えるさまざまな知識や技術について学んでいる。
衛星やドローンを用いた測量、施工の手順や安全管理、現場見学ではARを用いた空間の可視化や、IOTによってその全体がリアルタイムでつながる施工の様子など、日々目の当たりにしている。それは、幼い私が考えもしなかった未来の建設業の姿である。
現代の構造物は、最新のデジタル技術によって効率的に創られるため、無機質で冷たく感じられることもあるかもしれない。しかし、その背景には、長年の経験を積み重ねてきた職人たちの技術や知識がしっかりと根づいている。建築に携わってきた人々の数だけ、載せた想いが、目には見えないけれど確かに構造物に宿っているのだと確信する。建設するとは、目に見える構造物を、創ることに加え、人々の暮らしや想いが交差する場を作り上げていくことであり、誰かの今日を守り、その先も寄り添っていくことだと考える。
私は建設産業に、心から敬意を抱いている。それは古き社を守り、町並みを今につないできた職人たちすべてを支える、「誰かのために」というまっすぐな想いに触れているからに違いない。
いつか私も、建設業を通して、その想いをしっかり受け取り、次の世代へと手渡していける人間になりたい。汗にまみれた努力も、積み重ねた時間も、誰かの暮らしや心の拠りどころとして、静かに息づき続ける。そのように、未来へと続く一歩に、自らも関わっていきたい。その実現のためにも、私は心惹かれた構造物に自ら足を運び、その技術をこの目で直に感じ、さらに、新たな視点からも構造物をとらえ、誰かを支えられる技術者になりたい。その夢が実現するとき、あの日、神社の静けさに心惹かれていた、幼い日の私がきっと一番喜んでくれると思う。
私たちの主張 国土交通大臣賞 受賞作品
こうじげんばのひと

株式会社香山組(兵庫県建設業協会)
寺田 昌司 さん
| 受賞者へインタビュー |
|
■Q1 受賞された感想を教えてください。 ■Q2 建設業へ入職したきっかけを教えてください。 ■Q3 現在はどのようなお仕事をされていますか? ■Q4 今後の目標を教えてください。 |
「パパは工事現場でどんなお仕事をしているの?」6歳の息子からのストレートな質問に私は一瞬、言葉に詰まった。
私は「建設ディレクター」として工事書類を作成したり、三次元モデルを作ったり、現場技術者と協働して工事の進行を支援する仕事をしている。しかし、その仕事をどう伝えていいのかが、分からなかった。
建設業界に入職して4年が経つ。以前は鉄鋼メーカーで勤務をしていた私は、BIM/CIMモデルを作成するCADオペレーターの仕事に魅力を感じ、未経験のままコロナ禍真っ只中で転職を決意した。最初は右も左も分からず、毎日が手探りだった。それでも、三次元モデルを使った業務は、工事の内容を“見える化”できる特性があり、現場技術者とのコミュニケーションは取りやすかった。また、未経験だったからこそ「知らない人の目線」で、工事の目的や重要性をわかりやすく伝えることができたと思う。
この業界に入ってから、何人もの仲間が去っていく背中を見送ってきた。担い手不足や厳しい労働環境など、業界が抱える課題は少なくない。それでも私はこの仕事が好きだ。だからこそ、もっと多くの人に建設業の魅力を伝えていきたいと考えるようになった。
入社からちょうど1年が経つ頃、私は国土交通省が掲げる、デジタル技術を活用して工事の効率化を図る「インフラ分野のDX」の考えに共感し、「DX推進部を立ち上げたい」と会社に提案した。当時、業界経験の浅い私に対し、周囲の反応は冷ややかだったが、社長だけは「やってみましょう」と背中を押してくれた。
部を立ち上げてからは、工事の生産性向上に加えて、地域や子どもたちに工事の面白さを伝えることに力を入れた。作成したCIMモデルを活用して、普段一般の方が入れない現場をバーチャルで再現し、VRゴーグルをつけて体験してもらったり、夜のイベント会場では重機にイルミネーションを飾りつけて展示したり、近隣の保育園や小学校と一緒にクリスマスイベントも開催した。現場やイベントに来てくれた子どもたちが「工事現場っておもしろいね!」「また遊びに来てもいい?」と目を輝かせてくれた瞬間、私はこの取り組みの意義を確信した。
建設業は、何よりも「チームでつくる仕事」だ。施工管理、測量士、建設技能者、重機オペレーター、そして私のような建設ディレクター。それぞれが専門性を活かし、朝から日が暮れるまで一つの目標に向かってひた走る。そして完成した工事は「工事成績評定点」という形で評価され、良かった点も悪かった点も工事期間のすべての努力がフィードバックとして返ってくる。どれだけ優秀なホームランバッターがいても、チームにキャッチャーもピッチャーもいなければ、試合には勝てない。現場で共に働くそれぞれの分野のスペシャリストが力を出し合い、多様な技術と情熱が集まり、一つの「ものづくり」が形になっていく。この「チームでつくる力」に私は心から魅力を感じている。
最近では、建設業に興味はあるが、現場での作業に不安を感じている人も多い。だからこそ、「自分にもできるかもしれない」という新たなキャリアの選択肢として、建設産業の多様な関わり方を発信していきたい。年齢や性別、経験の有無に関係なく、「やってみたい」という情熱があれば、誰だって活躍できる場がここにはある。
ある日、現場から直行して作業着のまま保育園に息子を迎えに行ったことがあった。普段の私は、他のお父さんたちに合わせてパリッとしたワイシャツを着ていたのだが、その日は園児たちが「すごい!工事現場の人だ!」と集まってきた。息子は誇らしげに私の隣に立っていた。汗臭く、お世辞にも綺麗とは言えない作業着の姿が、子どもたちの目には輝いて見えていたのだ。その時、私は気づいた。大人が思う「かっこいい」と、子どもたちが思う「かっこいい」は違うんだと。その日から、私は作業着のまま保育園に迎えにいくことをためらわなくなった。
野球選手やパティシエ、警察官、看護師。子どもたちの「将来なりたい職業」にはさまざまな夢が並ぶ。しかしその中に工事現場で働く仕事の名前はほとんど登場しない。なぜなら、これらの仕事にまだ統一された魅力的な呼び名が存在しないからだと私は考えている。だから私はあえて「こうじげんばのひと」と呼びたい。大人が思う、かっこいい呼び名ではないかもしれない。それでも、子どもたちは自然とそう呼び、憧れの眼差しを向けてくれている。
私は、未来を担う子どもたちの「将来なりたい職業」に、「こうじげんばのひと」が当り前に並ぶような時代をつくりたい。建設業には、誰かの暮らしを支え、未来をつくる力がある。その素晴らしさを、幼い頃から子どもたちに伝えていきたい。将来の担い手は、今、目の前で遊んでいる子どもたちなのだから。
私はこれからも「こうじげんばのひと」として、建設業の魅力を伝え続けていく。
【冊子PDFはこちら】