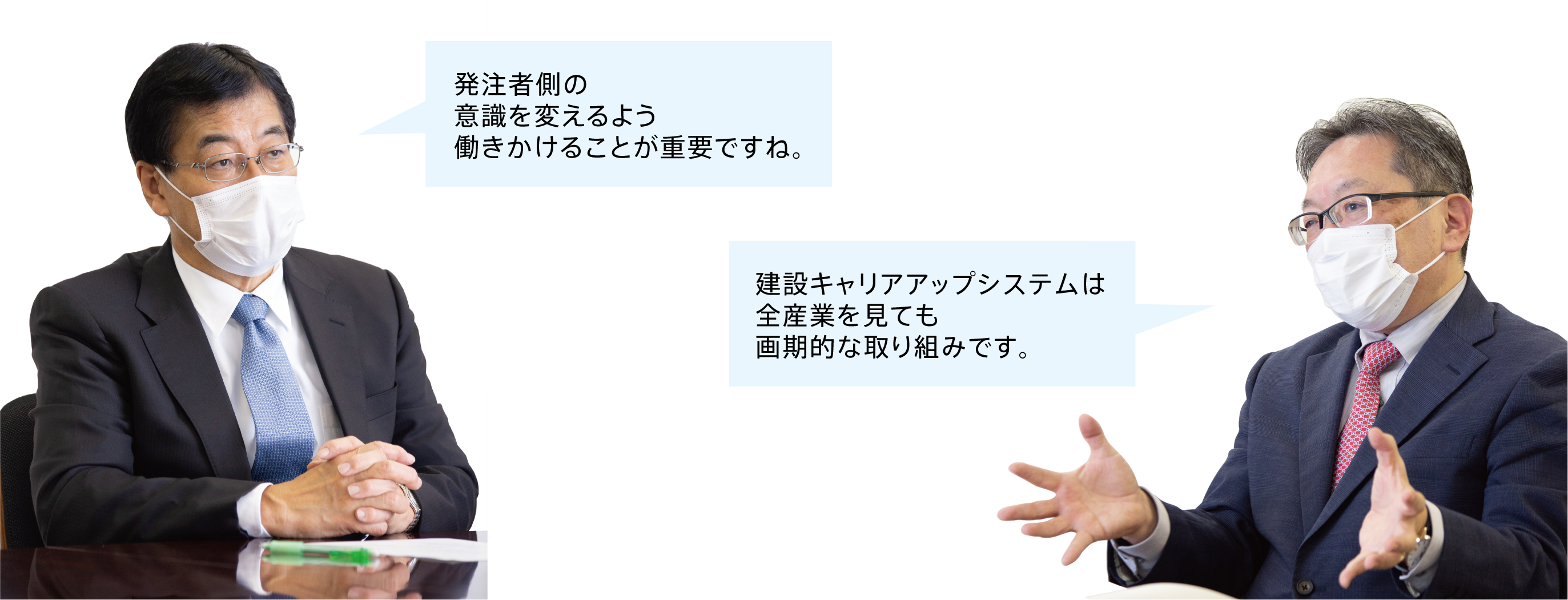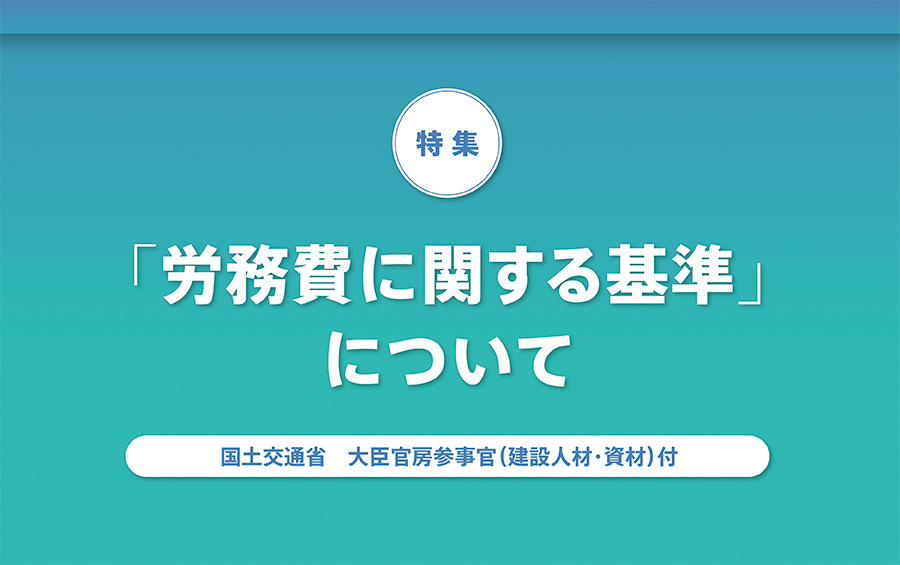特集
新たな時代の転換期に見る 建設業の課題と展望
賃金「2%アップ」を目標に。技能者を守るCCUSも推進。
佐々木 : 建設業界を見ても「安ければいい」という世間の考え方に慣れてしまっている現状があるように感じます。発注者側の意識を変えるよう働きかけることは、非常に重要ですね。また国土交通省としては、建設技能者賃金の「2%アップ」という目標値を掲げられました。意識転換を促す意味でも良い宣言だと感じるのですが、一方で一部の地域や職種ではダンピング受注が始まっているという声も耳にします。デフレが続く中、かつ「2%アップ」を目標とする中で、賃金の引き上げをどのように進められていくのか、考えを教えていただけますでしょうか。これからの労務単価も気になるところです。
長橋 : 労務単価については2021年3月に特例措置を講じましたが、実際問題としてコロナ禍の影響で発注が絞られているケースや、公共発注が落ち着いたタイミングでダンピング受注が起きてしまっている事例もあると聞きます。先ほど申したとおり、建設業全体の投資額や賃金が上昇した事実はあっても、様々な部分でギャップも生まれており、おしなべてうまくいっているとは言い切れません。専門工事団体の方々からもダンピング受注の防止施策を求められていますので、「2%アップ」という一つの目安のもと、様々な号令をかけていきたいと考えています。取引においては「どこまでが適正か」というラインはまだ曖昧なため、どのような根拠に基づき、どういったやり方をとるかという点は十分に検討する必要がありますが、行政としては行き過ぎた契約に対して警鐘を鳴らし、適正化を図る心づもりです。建設投資など業界全体のボリュームを増やすだけでなく、それがしっかりと皆に行き渡るよう、適切な配分に気を配っていくことが大切です。そうした面も政府として取り組みたいですね。
佐々木 : ありがとうございます。そうした賃金の話とも関連しますが、私たち建設業振興基金でも懸命に取り組んでいる建設キャリアアップシステム(CCUS)について伺いたいと思います。
すでに相当数の方が登録を進めており、今後はいかにそれを活かしていくかという状況ではありますが、業界内では未だ「メリットが見えない」「どんな価値があるのか」といった声を耳にすることがあります。賃金の引き上げに結びついていけば非常に意義のあるシステムではあるのですが、改めてこの建設キャリアアップシステムの役割や意義について、局長の考えを教えていただけますか。
長橋 : はい。さかのぼれば10年前の当時から有識者会議を含めて議論されていたのが、元下間において「下請をどのような指標で評価すればよいか」という点でした。そうした中で技能者の処遇を確保する施策の一つとして生まれたのが、今取り組まれている建設キャリアアップシステムです。特に若い世代に伝えたいのですが、このシステムはその人自身が努力したことや経験したこと、身につけた実力などをしっかりと蓄積し証明してくれるシステムであるということです。その人の能力を保証し、将来的にも守ってくれるような存在でもあるので、そうした理解とともに広く浸透するよう促していきたいですね。またこれは我々の課題でもありますが、そうしたシステムで紐づけられた評価が、技能者自身の賃金に反映されていくよう企業に働きかけていく必要があります。また、そうした処遇に取り組んだ企業を適切に評価する仕組みをつくることで、本当に意義のあるものになっていくと思われます。すでに取り組まれている企業もありますが、やはり業界全体のインフラになるべきシステムであると考えると、全ての企業に取り組んでもらい、共有財産としていただくことこそが我々が目指す形です。建設キャリアアップシステムのさらなる普及・推進に向けては、根本的に理解していただくことが大切ですので、より丁寧に説明していく必要性があるとも感じています。このシステムは全産業を見ても画期的な取り組みですので、しっかりと進ませ、根付かせていきたいです。
佐々木 : そうですね。建設キャリアアップシステムは、人手不足や求人難で四苦八苦する他の業界からも着目されている取り組みです。私たちも全力で普及に努めたいと思います。