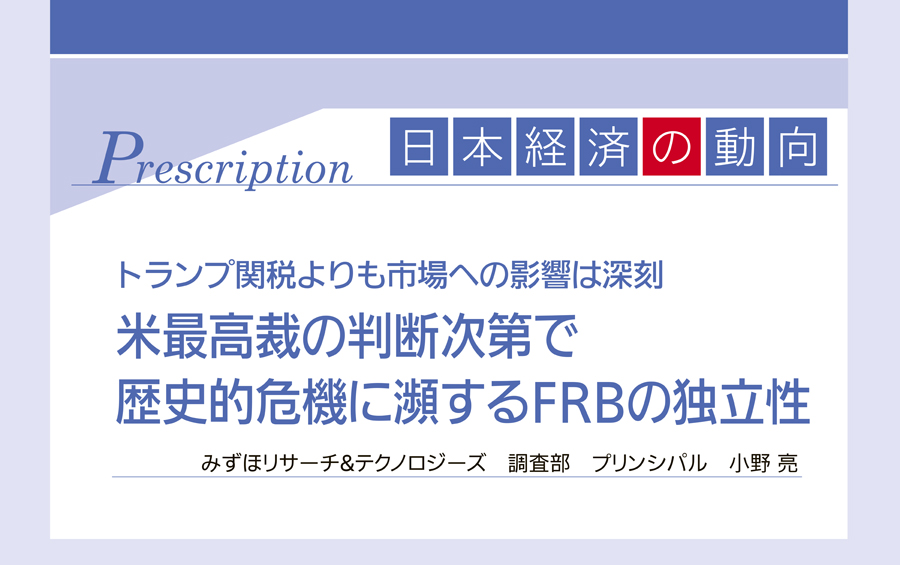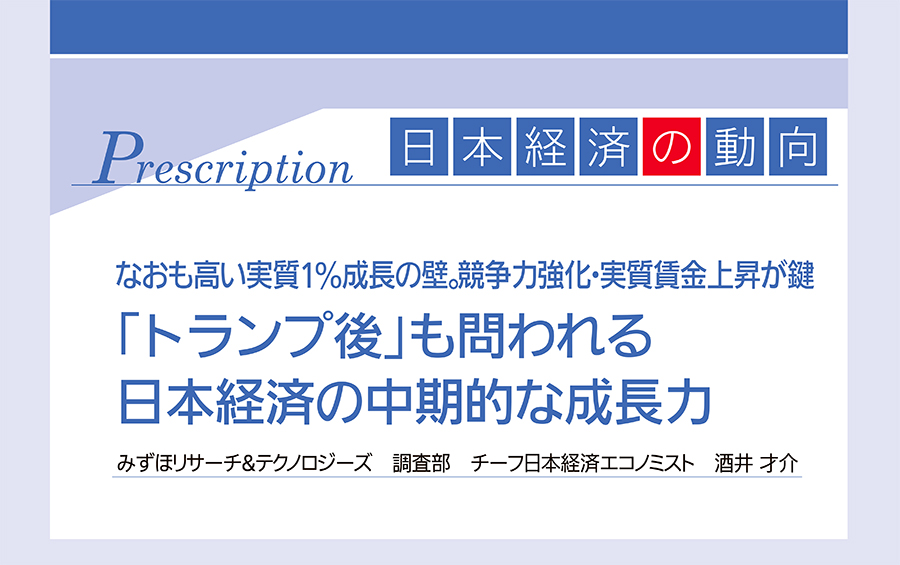日本経済の動向
日本のサプライチェーンを再検証する
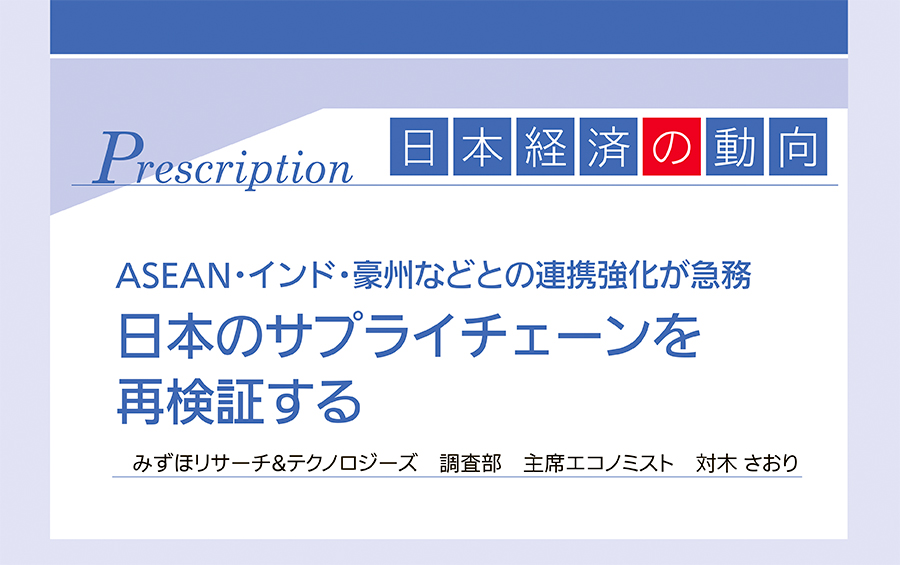
トランプ関税で世界貿易は縮小リスクに直面している。こうした中、日本としては、中長期的な視点でグローバル・サプライチェーンを強化する戦略が重要になる。そこで今回は、日本や各国が直面する輸入面での脆弱性を検証し、日本の立ち位置やサプライチェーン強化についての論点を紹介する。
貿易停滞は複雑なサプライチェーンに悪影響も
世界貿易の拡大は過去の世界の経済成長のドライバーとなってきた。関税政策により各国の貿易が停滞することになれば、米国との貿易に関する複雑なサプライチェーンを取り巻く数多くの地域・国の経済活動に悪影響を与える可能性がある。
わが国としては、米国との2カ国間の関税交渉も言うまでもなく重要だが、基本的な方向性としては、自国の貿易面での脆弱性を早急に再検証すべきであろう。日本にとっては、米国を軸とする先進国のみが主要な貿易パートナーではなく、近年範囲を拡大しつつあるBRICSをはじめとする新興国も重要度を増している。加えて、日本企業の活動は海外生産や貿易を通じて多角化しており、米国やEUのみに焦点を当てるのは効果的とは言えず、新興国との関係に目配りすることも必要だ。
日本と新興国は共通の脆弱性に直面
では、日本は実際にどのような物品について輸入面の脆弱性を抱えているだろうか。ここでは、ある財の輸入先がどれだけ特定の国・地域に集中しているかを示す「輸入集中度」を脆弱性の指標として用い、サプライチェーン上戦略的に重要な財について輸入集中度が高いものをリストアップした(2023年時点)。なお、輸入集中度の計測方法や基準、具体的な財のリストについて、詳細な内容は、みずほインサイト「拡大するBRICSとサプライチェーン」(2025年2月10日)を参照してほしい。
結果を見ると、資源関連で輸入集中度の高い財が多い。具体的には、マンガンは南アフリカからの輸入割合(マンガン鉱石:輸入依存度69.1%、マンガン:同35.0%)が高い。また、長石、ルネサイト等(中国:輸入依存度82.6%)、ジルコニウム(豪州:同59.1%)、世界的に供給難問題があるヘリウム(米国:同66.5%、フランス:同32.3%)などがあげられる。資源を海外に依存する日本としては、原材料で輸入面の脆弱性が高いのは致し方ない面もある。
一方、気になるのは一部の電子機器・部品でも同様に輸入集中度が高く、かつその輸入先を中国に依存している点である。輸入集中度が高い14品目中、7品目で中国依存度が30%を超えており、具体的な品目では電子機器・部品関連が多く、自動データ処理機械(PC等)(中国:輸入依存度98.7%)、リチウムイオン電池(中国:同73.1%)で極めて高い中国依存度が確認できる。
他の主要地域・国の脆弱性を同じ戦略財で比較してみると、アジア新興国地域でも同様の課題を抱えている状況であることが分かる。まず、2019年と2023年(ASEANは2022年データ)の品目数の変化をみると、米中対立の中で新たな生産拠点として注目を集めているインドやASEAN、また自動車などの現地生産強化を行っている南アフリカにおいて、輸入集中度の数値の高い脆弱財の数がそれぞれ大幅に増加している。さらにこれらの財のうち、豪州やインド、ASEANでは、中国依存度が高まる財が増加傾向にあり、リチウムイオン電池やPC、スタティックコンバーターなど、中国産の電子機器や部品への輸入依存度が高いケースも散見される。特に、インド、ASEANでは、米中対立の影響と地政学リスクの高まりを背景に中国からの生産移管先として存在感を強めているとは言え、製造業の生産能力が未成熟で、むしろ中国からの製品・部品輸入に依存する構造となっている。こうした新興国におけるサプライチェーン上の脆弱性への取り組みは、日本とも共通の課題であるといえよう。
日本にはリーダーシップの発揮を期待
日本政府としては、同じような課題に直面するASEANや、インド、さらには豪州との連携を進める必要がある。貿易の不確実性が高まる中でも、各国の貿易構造や産業構造を相互に理解・把握し、最適なグローバル・サプライチェーンを模索する視点が重要度を増すであろう。さらに、日本としては、2017年の米国のTPP離脱後も、各国との連携を強め、2018年に発効したCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)での実績がある。2024年末の英国のCPTPP正式加盟の実現、さらにはEUがCPTPP加盟国との連携に関心を寄せる中、自由貿易体制の拡大に向け日本としてもリーダーシップを発揮することが期待されている。
【冊子PDFはこちら】