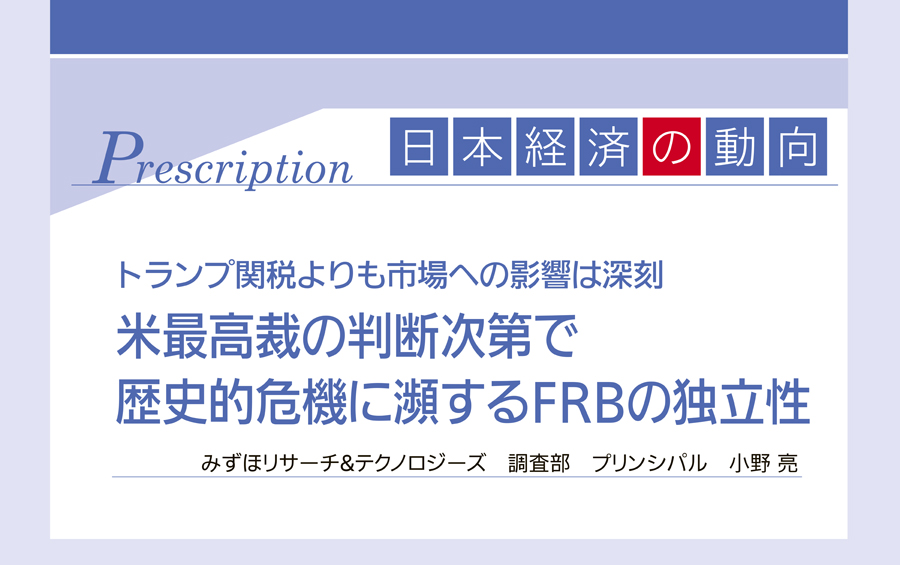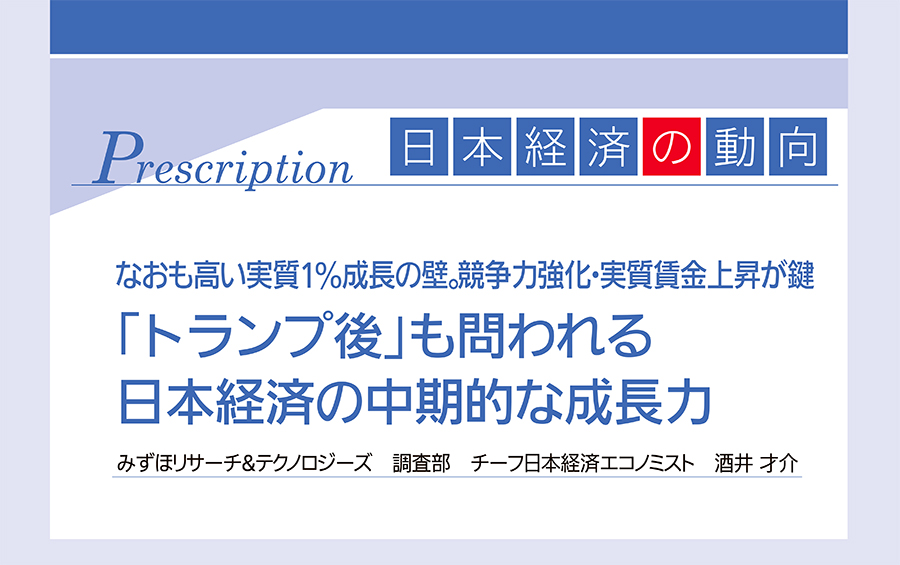日本経済の動向
中国の物価動向とビジネス環境
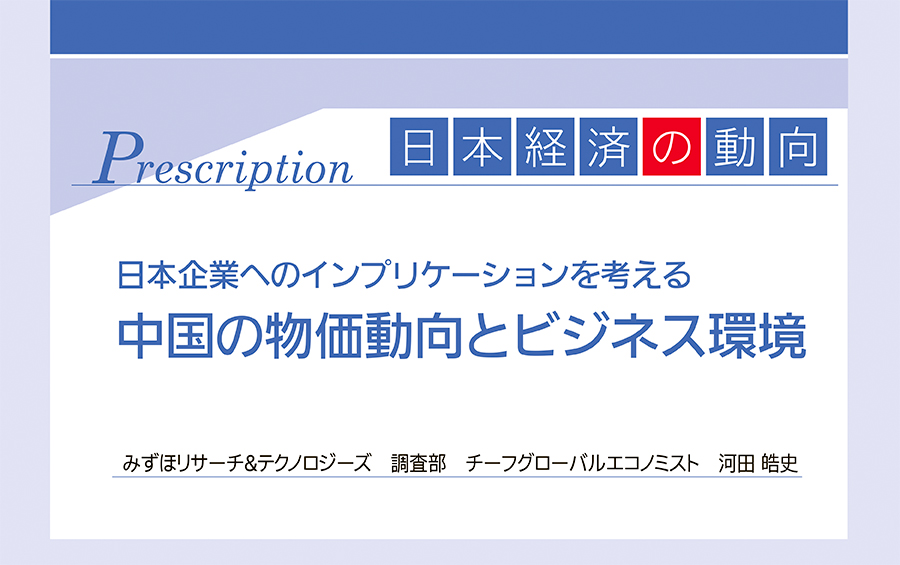
中国の物価は弱めの動きが続いている。物価の弱さは一国全体でみた企業収益の弱さにつながるため、日本企業の中国ビジネスにおいても懸念される要素だ。一方、物価の弱さが今後も続くのであれば、デフレビジネスに強みを持つ日本企業にとってはチャンスとなる可能性もある。今回は、中国の物価の弱さの背景と、中国ビジネスを行う日本企業へのインプリケーションについて解説する。
需給の緩みから物価の弱さが続く中国
中国の実質GDP成長率は趨勢的に鈍化している。2000年代に10%を超えていた成長率は、2010年代には7%前後に鈍化し、近年は5%前後で推移している。人口減少や不動産問題といった構造問題にトランプ関税の影響も加わり、先行きも成長ペースの鈍化が続くと見込まれている。例えば、25年7月のIMF(国際通貨基金)の見通しでは、25年は4.8%、26年は4.2%と、いずれも4%台の成長が予想されている。
このように成長率が鈍化し、需要の拡大ペースが鈍くなる中で、物価も弱めの動きとなっている。消費者物価は前年比0%前後の動きが続いているほか、生産者物価は前年比▲2~▲3%程度の下落が続いている。経済全体の物価に相当するGDPデフレーターも9四半期連続で下落している。
この弱い物価の背景には、需要の伸び悩みに加えて慢性的な過剰供給という問題がある。実際、各種のデータを用いて中国の需給バランスを推計すると、過去数年にわたって需要不足・供給超過が続く格好である。需給の緩みがデフレ圧力になっていると考えられる。
今後も物価は伸び悩む見込み
こうしたデフレ圧力は近いうちに解消するのだろうか。この点について、需要面・供給面の両面から検討してみよう。需要面のうち、内需はこのところ個人消費を中心に底堅く推移している。ただし、これは政府の耐久財買い替え補助金に支えられている部分が大きく、同補助金が終了した後には反動減が見込まれる。不動産市場の調整が続く中、住宅価格下落による逆資産効果が下押し要因となっていることもあり、下期にかけて内需は減速していく可能性が高い。外需もトランプ関税という逆風があるため、しばらくは強気になれないだろう。全体として、需要面の減速感は本年下期にかけて強まることが予想される。
供給面はどうだろうか。従前より中国では過剰投資が指摘されてきた。長期的には是正の方向にあるように見受けられるが、それでもなお資本減耗を大きく上回る資本形成が行われている姿に変わりはなく、生産能力としての資本ストックの拡充がハイペースで進められている状況である。需要が伸び悩む状況で供給能力を急激に拡大しているわけなので、需給が緩むのは必然である。以上を総合すると、需給の緩みが直ちに解消されるイメージは持ちにくく、したがって当面は現状程度の弱めの物価動向が続く可能性が高い。
それでも大きいパイの増加量
実質GDP成長率の減速に物価の弱さが加わり、中国の名目GDP成長率は直近25年4~6月に3.9%と4%を割り込んだ。中国国内の企業収益は基本的には名目GDPに連動するため、名目GDPが伸びにくくなれば、現地の日本企業のビジネス環境も明るくなりにくい状況が続くことが想定される。
一方、成長率の分母となるGDP規模が昔に比べてかなり大きくなっていることも重要な事実である。つまり、これだけ成長率が減速しても、中国で1年間に増えるGDPの総量はASEAN主要国1カ国分のGDP規模を上回る。毎年ASEAN1カ国分ものパイが拡大する市場は、米国以外には中国しか存在しない。競争環境が厳しさを増すなど中国ビジネスには難しい部分も多いのは事実だが、そうはいってもポテンシャルの極めて大きい、魅力ある市場であることもまた事実である。
デフレ経験値を積んだ日本企業には商機
中国の物価の弱さは日本企業にとってはチャンスとみることもできる。つまり、長くデフレに苦しんだ日本市場でのビジネス経験を豊富に有する日本企業は、「デフレ経験値」においては優位性を持っているからだ。消費者の低価格志向が強まる中で利益を出すノウハウを蓄積しているということは、物価が上がらない経済における勝ち方を知っていることと同義である。
日本のデフレ期の経験を踏まえると、中国のB to C市場でも今後「優勝劣敗」が鮮明になっていくことが予想される。この点、デフレあるいはゼロインフレ経済における「勝ち筋」を知る企業には大きなチャンスが到来していると言えるだろう。
【冊子PDFはこちら】