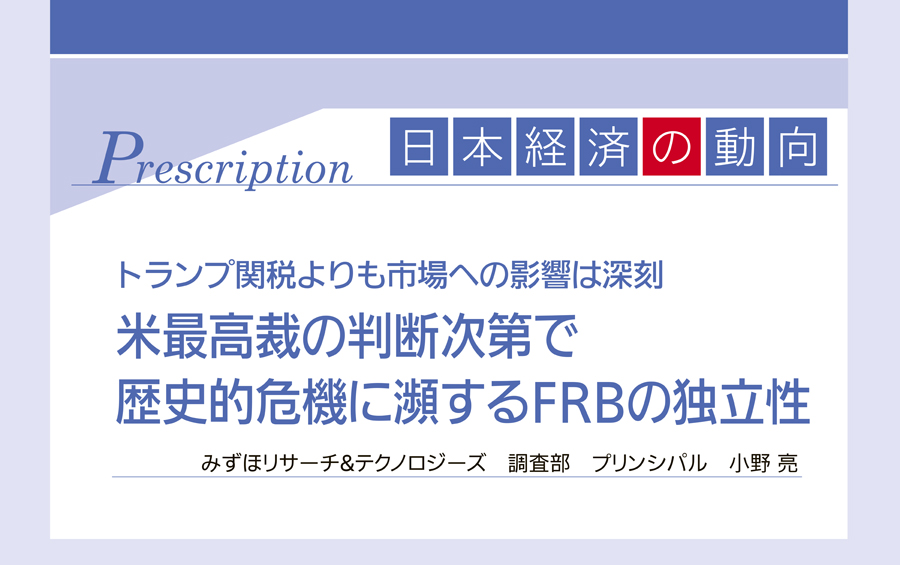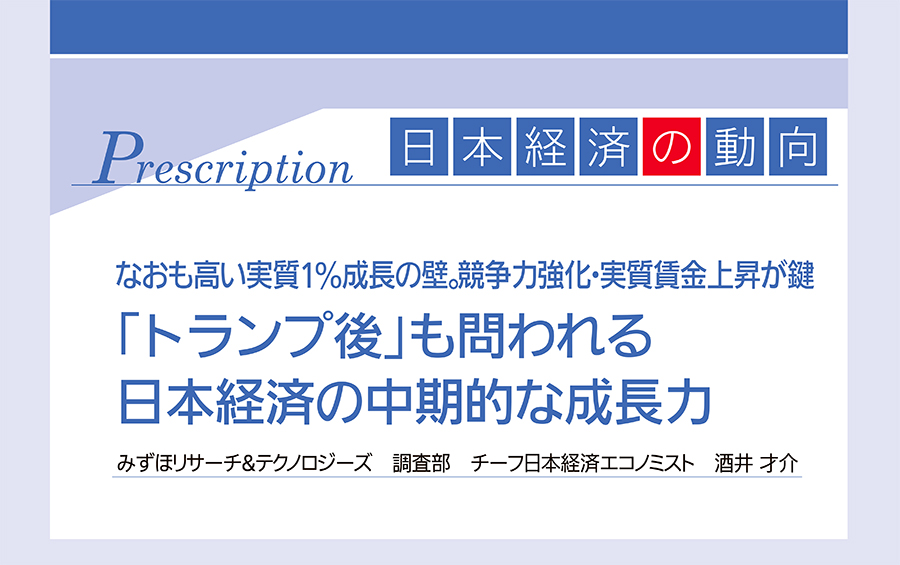日本経済の動向
トランプ氏だけが理由ではない米国の内向き志向
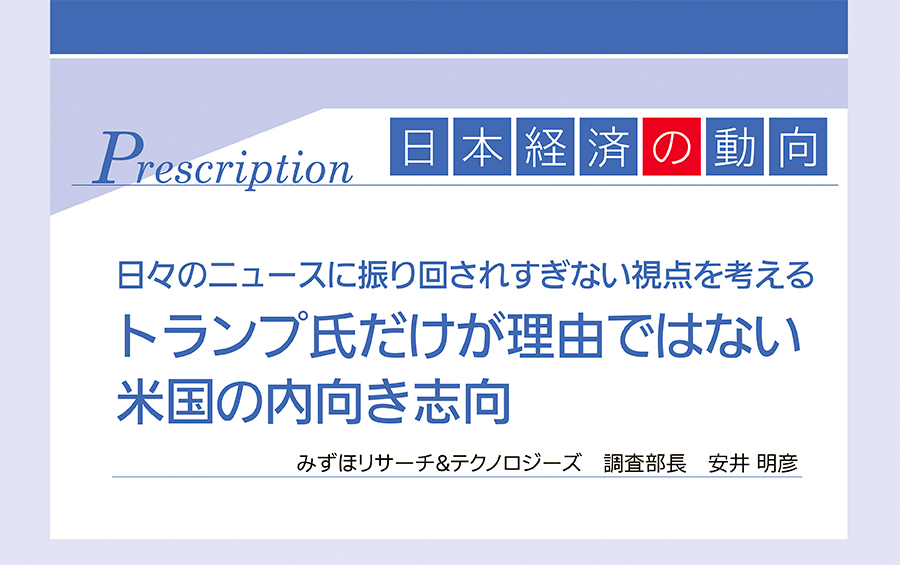
米国トランプ政権の通商政策が、企業の経営判断を難しくしている。特に関税の行方はトランプ大統領の意向に左右されやすく、先行きの不透明性は高い。もっとも、トランプ政権が発足する前から、米国の内向き志向が強まっていたことは見逃せない。今回は、日々のニュースに振り回されすぎないために、今後の対米ビジネスを考えるうえで大切な、米国世論の潮流を紹介する。
トランプ政権より前からあった内向き志向
米国トランプ政権の通商政策は、外交上の友好関係よりも、米国の利益を第一に考える「米国第一主義」の表れだ。その背景には、「外交政策よりも、自国経済の立て直しを優先してほしい」という、米国世論の「内向き志向」がある。ピュー・リサーチセンターが2024年4月に行った世論調査では、「米国の大統領は内政を優先すべきだ」とする回答が8割を超え、「外交を優先すべきだ」との回答は1割強にとどまっていた。
見逃せないのは、内向き志向の高まりが、トランプ政権の発足に先立っていることだ。米国世論が内向き志向なのは、トランプ大統領に感化されたからではない。米国世論が内向き志向だからこそ、米国第一主義のトランプ氏が大統領に選ばれたとみるべきだろう。
同センターが07年1月に行った世論調査では、内政と外交を優先する回答が、それぞれ約4割で同程度だったが、それ以降は内政を重視する割合が増加傾向をたどっており、オバマ政権下の12年1月に行われた調査では、既に現在と同程度の8割強に達していた。
内向き志向の背景に、将来への期待の陰り
内向き志向の理由がトランプ氏だけでないのであれば、トランプ氏の支持率が低下したり、28年の次の大統領選挙で政権が交代したりしても、米国第一主義は続く可能性がある。むしろ先を読むうえで重要なのは、そもそも米国世論が内向き志向になった理由が解消するかどうかだ。
経済の観点では、米国世論の内向き志向の背景には、「暮らしを良くしてほしい」という願いがありそうだ。内向き志向の強さは長期間にわたっており、こうした世論の願いが、短期的な景気の浮き沈みだけに左右されているわけではないことがうかがえる。考えられるのは、将来への期待の陰りだ。米国では所得格差の拡大と固定化が著しく、低所得の家庭に生まれると、努力しても富裕層になりにくい傾向が強まっている。米国ウォールストリートジャーナル紙が23年3月に行った世論調査では、「次の世代は自分たちよりも良い暮らしができる」と信じる割合が2割程度にとどまり、約半数だった01年12月の調査結果からの低下傾向が続いている。アメリカン・ドリームの中核ともいうべき次世代の暮らしへの期待の陰りが、内向き志向が定着する土壌になっている可能性がある。
国際貿易への期待は高まっている
一方で、米国世論の内向き志向の高まりは、国際貿易への反感によるものではなさそうな点には注意が必要だ。トランプ政権が目指す貿易相手国の市場開放や貿易赤字の削減だけでは、内向き志向の改善は保証されない。必要なのは、米国国民の暮らしが改善し、将来への期待が復活することだ。
そもそも米国では、通商政策への関心が低い。24年1月にピュー・リサーチセンターが政権の優先課題をたずねた世論調査によれば、通商政策を選ぶ割合は、経済、教育などの20の選択肢のなかで、もっとも低い3割程度だった。同センターによる25年1月の同種の調査では、通商政策は選択肢にすら含まれていなかった。また、25年4月にギャラップ社が行った世論調査では、8割が国際貿易を「経済成長の機会」として前向きに捉えている。08年の調査では同じ回答は4割程度に過ぎず、内向き志向が強まっていった時期でも、国際貿易への期待は高まっていたことになる。
カギを握る次世代の期待回復
米国の政治は、世代交代の時期に差し掛かっている。1993年就任のクリントン大統領以来、ベビー・ブーマー(1946年~64年生まれ)以前の世代の大統領が続いてきたが、2028年の大統領選挙では、若い世代の大統領となる可能性が高い。ちなみに、トランプ政権のバンス副大統領は、ミレニアル世代(1981年~96年生まれ)の政治家である。
有権者においては、既にベビー・ブーマー世代は最大勢力ではなく、ミレニアル世代以降の発言力が増している。世論調査では、これらの世代は暮らし向きへの懸念が強く、先行する世代よりも内向き志向が強い傾向がある。例えば、シカゴ国際問題評議会が2023年9月に行った世論調査では、ミレニアル世代の回答者の5割が「米国は国際問題から距離を置くべきだ」と答えており、3割程度だったベビー・ブーマー世代を上回った。米国のこれからを担う世代が将来への期待を取り戻せるかどうかが、米国が内向き志向を脱却するカギになりそうだ。
【冊子PDFはこちら】