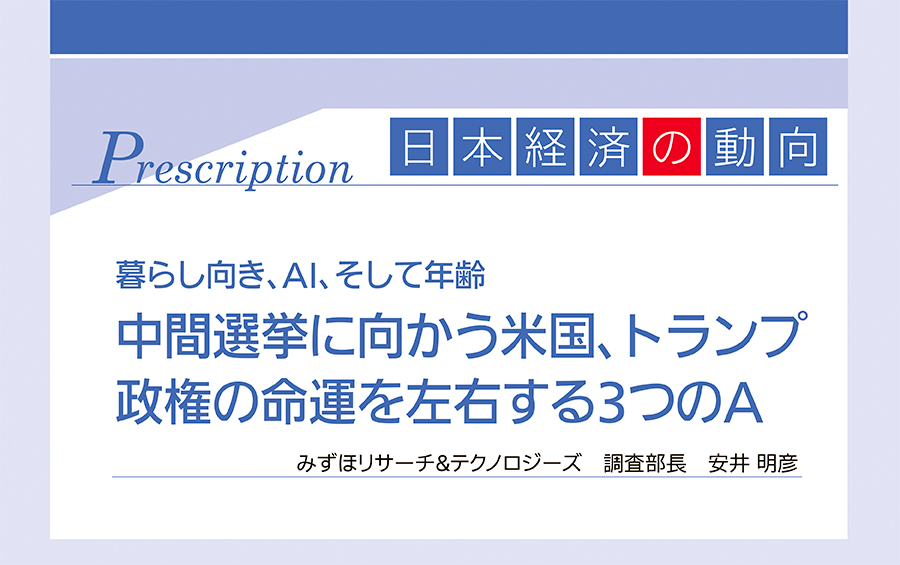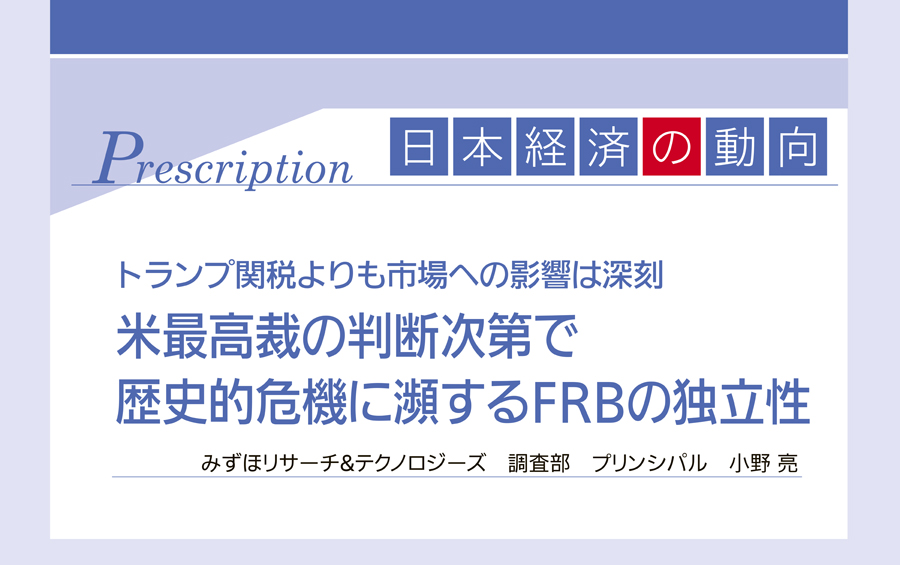日本経済の動向
在庫のある世界
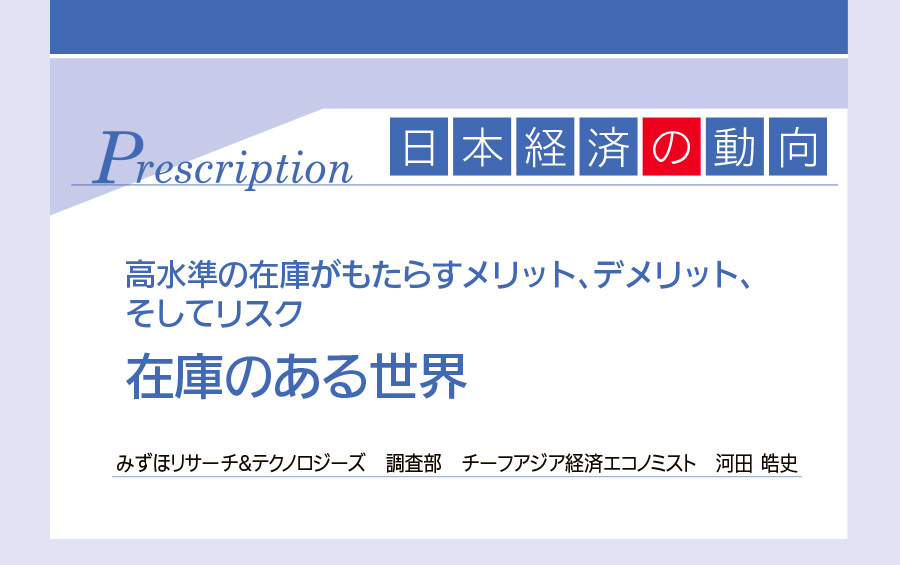
経済活動対比で在庫が高水準となっている。通常、在庫の増減は景気循環(好況・不況)との関係で議論されることが多いが、近年の持続的な在庫増加は循環を超えたトレンドのようにも見える。そこで今回は、近年の在庫増加の背景とそのマクロ経済に対するインプリケーションについて解説する。
経済活動対比で高水準の在庫
在庫が増えている。メーカーの製品在庫の「在庫率」(在庫量を出荷量で割ったもの)は、2000年代半ば頃と比べ、現在の水準は50%以上切り上がっており、メーカーは昔に比べてかなり多くの在庫を抱えるようになっている。
在庫率は景気に対して反循環的に動く性質がある(=景気が悪いときに上昇し、景気が良いときに下落する)。特に、リーマンショックやコロナショックのように需要が急減する場合には、分母である出荷の急減により在庫率は大幅に上昇する。
在庫率の短期的な上昇・下落は景気循環に対応するものと理解しておけばいいが、近年の持続的な上昇は単なる景気循環の域を超えた動きのように見える。日本の実体経済が総じて冴えないのは事実だが、単に需要が弱いだけなら在庫が長期的に積み上がり続けるとは考えにくいため、それ以外の要因があると考えるのが自然だろう。
東日本大震災とコロナ禍が契機に
在庫率の上昇トレンドが明確になったのは2010年代前半だが、この時期にあった大事件は東日本大震災である。東日本大震災の際には、地震・津波により被災地の生産設備が破壊されたことに加え、道路や空港などの物流インフラも相当のダメージを受けたことから、多くの製品の供給が途絶えることとなった。結果として、被災地以外でも部材不足により生産活動に多大な影響が出たため、企業はサプライチェーンの管理まで含めた事業継続計画(BCP)が必要との教訓を得ることとなった。こうした流れの中で、最終財メーカーは部材在庫を積み増し、部材メーカーは製品在庫を積み増す傾向が強まった。
在庫率の上昇トレンドはコロナ禍以降に加速したが、これについては2021~22年頃の「モノ不足」、特に「半導体不足」の経験が影響していると思われる。半導体などのモノ不足により、企業の生産活動が強く制約された経験を通じて、財の生産・流通における複数の段階で、各種の在庫を積み増す動きが強まったものとみられる。
高水準の在庫は経済に何をもたらすのか
高水準の在庫は経済に何をもたらすのだろうか。ポジティブな側面としては、自然災害などの供給減少ショックへの耐性が高まることが挙げられる。また、在庫保有の最大の理由が「販売機会を逃さない」ことだとすれば、2021~22年頃にみられたような財需要の急激な高まりが先行きどこかで生じた場合に、需要に供給が追い付かないことによる「売り逃し」を回避することも期待されるだろう。
一方、在庫増加にはネガティブな側面もある。企業経営・企業会計の観点では、在庫増加はキャッシュフローの悪化につながるため、通常は好ましくないこととされる。企業金融面からみると、こうしたキャッシュフローの悪化は、外部資金需要を高めることにつながる。実際、在庫率と運転資金の動きを比較すると強い相関があり、在庫の増減によるキャッシュフロー動向見合いで、運転資金の調達が行われることがよくわかる。
また、何らかの需要減少ショック(例えば海外経済成長率の大幅減速)が発生した場合には、企業は多かれ少なかれ在庫調整を進めざるを得ないが、こうした場合には、高水準の在庫が経営の重荷になる可能性が高い。
「逆回転」のリスクには要注意
企業はこれまでさまざまな理由により意図的に在庫を積み増してきたとみられるが、こうした在庫保有スタンスが今後も続くかどうかは不透明である。東日本大震災以降のBCP対応による在庫積み増しが巻き戻される可能性は低いと思われるが、コロナ禍以降の在庫積み増しは、「半導体不足」などの記憶が残る現時点では正当化されても、そうした記憶が薄らいでいくと巻き戻される可能性がある。こうした「逆回転」が実際に生じる場合には、在庫圧縮により生産活動には下押し圧力がかかる。
仮に、企業の在庫保有スタンスに変化が生じ、過去数年で増加した在庫を短期間で調整する場合には、実質GDP成長率に相応のマイナス寄与となる。米国における第二次トランプ政権誕生などもあり、海外経済に関する不確実性が高い状態が続く中、予期せぬ需要減少およびそれに伴う在庫調整圧力の高まりにも注意が必要になりつつあると言える。
【冊子PDFはこちら】