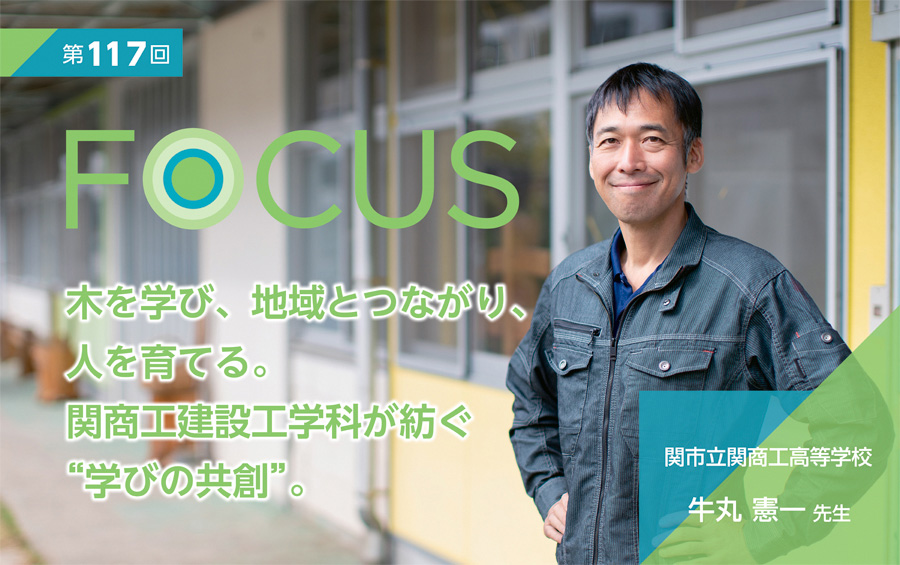FOCUS
“できる”を育て、前に進む生徒を支える。積み重ねで拓く、建築教育のあした。
現場と出会い、
社会を知る・学ぶ
地元の建設業協会や建築技術協会などと連携した現場見学会も実施している同校。
「皆様のご協力のもと、現場見学会を定期的に実施することができています。また、県内だけでなく、県外の都市圏で行われている大規模なプロジェクトの見学などにも参加するなど、幅広い現場を目にすることができるよう図っています。現場のスケール感やリアルな雰囲気に刺激を受けた生徒たちは、進路に向けた意識も大きく変わっていきますね」。
また、以前は卒業後に専門学校や大学への進学を選ぶ生徒も多かったが、近年の法改正により建築士の資格取得条件が緩和されたことで、変化も生じていると山田先生は話す。
「これまでは専門学校や大学の建築科を卒業しないと得られなかった2級建築士の受験資格が緩和され、資格取得のハードルが下がりました。進学せずとも建築士を目指せるようになったことで、就職を選ぶ生徒が増えているのは事実です。“最短で建築士になれる”ということは、建築科を擁する工業高校の大きなメリットと言えるでしょう。資格を持って社会に出ることができれば、大きな自信にもなります」。
生徒と歩む、
『有言実行』の教育
生徒には、建設業界で必要な“元気”と“挨拶”という基本を身に付けてほしい──。そんなシンプルかつ本質的な言葉を口にする山田先生。日々伝えているのは、『有言実行』の姿勢だ。
「“やると言ったことはやる”、“途中で投げ出さずやりきる”。そうすることで、初めて求めていた成果が手に入るものです。それは普段の勉強でも、資格取得でも、部活動においても言えること。生徒には『有言実行』の先にある“良い成果”を求めることを重視してほしいです」。
指導にあたって大事にしているのは、生徒一人ひとりに寄り添うということ。
「途中でくじけてしまったり、挫折したりすると、つい楽なほうへと行ってしまうのが人間。そうしたときに生徒に寄り添い、もう一歩引き上げ、背中を押してあげることこそが今の教育には大事だと感じています」。
昨年度には、中国地方の優秀卒業設計作品審査で最優秀賞を受賞する生徒も輩出している同科。山田先生も卒業設計の指導にあたった際には、生徒に寄り添い、作業時間が放課後や土日に及ぶ場合でも見守り続けるようにしている。
「卒業設計は軌道に乗るまでが本当に大変ですが、方向性が定まってからの生徒の集中力と成長は目を見張るものがあります。その努力が実を結ぶよう、私も時間を使ってより良い作品が作れるよう指導しています。そうした時間をともに過ごすうち、生徒が感謝の気持ちを抱いてくれるようになり、卒業式の日にはお礼の気持ちを伝えてくれました。生徒と一緒になって取り組んだ時間や“ありがとう”という言葉は、私にとっても大きな糧になっています」。
自身を“建築バカ”と形容する山田先生。実家が建設業に携わっていたこともあり、小さな頃からものづくりの道に魅せられていた。「学生のときはゼネコンで働きたいと考えており、教員になったのは偶然の縁。しかし、建物をつくることへの憧れはずっと胸にあります。そうした自分の夢を、生徒たちに託している部分もあるかもしれません(笑)」 。
これからの目標は、生徒に、そして若い先生方にも建築の面白さを伝えていくこと。
「得意を伸ばせば、不得意もカバーできる。ペーパーテストが苦手でも技能が得意なら、その道を活かせばいい。大切なのは、自分の強みを見つけることです。その強みをもって社会に出て、大いに活躍してほしいと思います!」。

県内外での現場見学や、足場・鉄筋などの技能分野の体験、地元のマイスターを招いての指導などにも積極的に取り組んでいる。「私たち教員のみで教えるばかりでは、学びや成長が停滞してしまいます。企業の方や現場の最前線で活躍されている方を招き、最新の技術や実践的な知識に触れる機会を取り入れるようにしています」。

小さな子どもたちに向けた取り組みにも力を入れている同校。幼稚園や保育園への出前授業では、バックホウの操作体験や木工教室、都市計画をテーマにしたワークショップなどを通じて、ものづくりの楽しさを伝えている。「子どもたちは、やっているこちらが驚くほど喜んでくれます。ものづくりに興味をもってもらう第一歩になれば嬉しいです」 。
|
邑南町立石見中学校
1968年に竣工した校舎の老朽化に伴う建て替えにより、2024年6月に完成を迎えた邑南町立石見中学校の新校舎。国内外でプロジェクトを手掛けるシーラカンスアンドアソシエイツが設計に携わり、教科ごとに専用の教室を備える『教科センター方式』を採用している。「生徒とともに改築工事の現場見学に伺った場所です。県内でも珍しい構造で、生徒たちも興味津々でした」。 |


島根県立松江工業高等学校
〒690‐0012 島根県松江市古志原4丁目1-10
WEB:https://www.matsue-th.ed.jp//
◎本誌記事の無断転載を固く禁じます。
【冊子PDFはこちら】