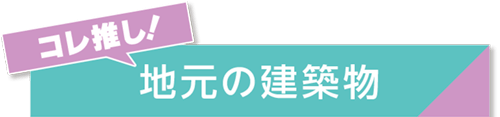FOCUS
10年に及ぶものづくり経験を生徒に還元!建築業界・工業教育の未来につながる取り組み。
住宅設計から
工業教育の道へ
教職に就く以前には、約10年にわたって民間企業で設計の仕事に従事していた大森先生。
「ハウスメーカーで設計の仕事をしていた中で、たまたま“講師をやってみないか”というお話をいただいたことが教職に転身するきっかけでした。企業から独立して自分自身の力で建築に携わっていく選択肢もあったのですが、教職に就いて生徒を育成することで、一人では成し得ない何倍もの力が生まれること、そして活躍する人材を輩出し続けることこそが建築業界に大きな風穴を開けることにもなると感じ、“工業高校の先生”という新たな道に進みました」。
1級建築士として建築業界で培った経験は、授業の中にも活かされている。
「授業では、私自身が設計した住宅の図面を教材として活用し、実際の業務に即した学びを提供しています。そうすることで、設計図に込めた明確な意図やリアルな仕事の流れを感じてくれるのではないかと思います。余談ですが、本校にも私がハウスメーカーに勤めていた頃に設計した家に住んでいる生徒が入学しました。設計当時はまだその生徒が生まれる前だったので、十数年を経ての不思議な縁に驚きました(笑)」
建築業界の担い手と
新たな後進を育む!
巣立っていった教え子たちの様子を知ることも、楽しみの一つになっている。
「卒業した生徒が来校し、“1級建築士の資格が取れました”と報告に来てくれたり、“先生が仰っていた意味が社会に出てみて分かった”といった言葉をかけてくれたりするなど、教え子たちが社会で活躍し、奮闘する様子を知ると、教師として感慨深いものがあります。また、教員の世界でも人材不足が大きな課題になっている中、大学へ進む生徒には“教員免許を取っておくことで選択肢が広がるよ”と話しているのですが、そうした教え子の中に教職の道に進む者も出てきました。自分の教えが何かしらの形で実っていくのを目にすると、嬉しい気持ちが湧いてきます」。
大森先生から生徒に贈るのは“Less is more”という言葉だ。
「20世紀に活躍した建築家、ミース・ファン・デル・ローエの言葉です。直訳すると“少ないほうが豊かである”となりますが、デザインを突き詰めていくと自ずと空間はシンプルになるといった意味です。建築の哲学・信念を示したものですが、今の生徒、今の世の中にも通じる言葉だと捉えています。スマホやアプリなど、便利だけれど複雑なものにあふれていると、徐々に自分を見失っていくものです。シンプルに自分の道を突き進んでいくことが、これからの時代は大切なのではないでしょうか」。
今後も一層、建築業界の担い手を輩出するとともに、新たな後進を育てていきたいと話す大森先生。
「担い手不足が叫ばれていますが、本校をはじめとした公立の工業高校自体もまた、生徒数の減少という課題に直面しています。自分たちの信念を大切にしながら指導を行い、もっと工業高校の魅力をアピールしながら、建築業界を背負って活躍する担い手を育てていきたいです。また、そうした中から私と同様、建築士の資格を持った教員が生まれ、より多くの生徒を育てて社会へと送り出す──。そんな流れを、周りを巻き込みながらつくっていきたいです。“建築の道に進もう”と決めて入学してくれた生徒たちが、心の底から魅力を感じ、活躍し続けていけるような業界づくりの一助になっていけたらと思います!」
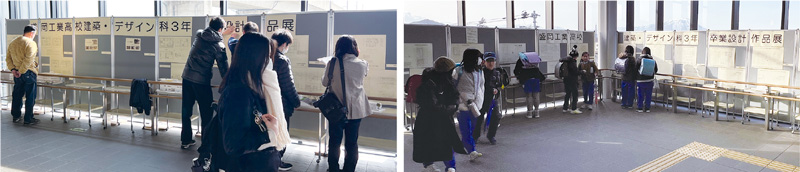
昨年には建築・デザイン科3年生の卒業設計作品をJR岩手飯岡駅の東西自由通路に展示。「例年は校内に掲示していましたが、少し視野を広げ、地域の方々や小中学生にも見ていただきたいと思い、作品展を開催しました。JRの利用者の方々にも目にしていただき、本科の取り組みを知っていただく機会になりました」
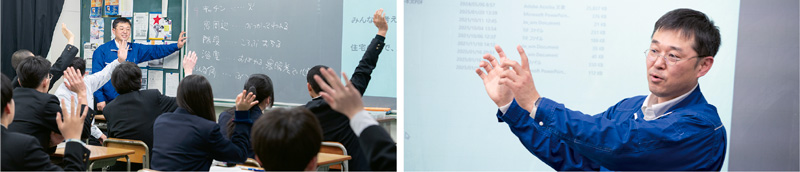
「今の生徒は昔と比べて“負荷がかかりにくい”時代を生きています。その分、つまずいたり、壁にぶつかった際に、あきらめずに立ち向かう力が育ちづらい環境にあるとも言えます。温かさや優しさも大切ですが、ときには厳しさを交えた指導により、“へこたれない力”を身につけていってほしいです」
|
岩手銀行(旧盛岡銀行)
通称“岩手銀行赤レンガ館”と呼ばれる国の重要文化財。東京駅の設計で知られる辰野・葛西建築設計事務所によるもので、詩人・宮沢賢治の詩にも詠われている盛岡のシンボルです。「著名な建築家である辰野金吾と、盛岡出身の葛西萬司が設計を手がけたものです。地元の方が携わった魅力ある建物として、広く世間に知られたらうれしいです」 |


岩手県立盛岡工業高等学校
〒020-0841 岩手県盛岡市羽場18-11-1
WEB:https://www2.iwate-ed.jp/mot-h/
◎本誌記事の無断転載を固く禁じます。
【冊子PDFはこちら】