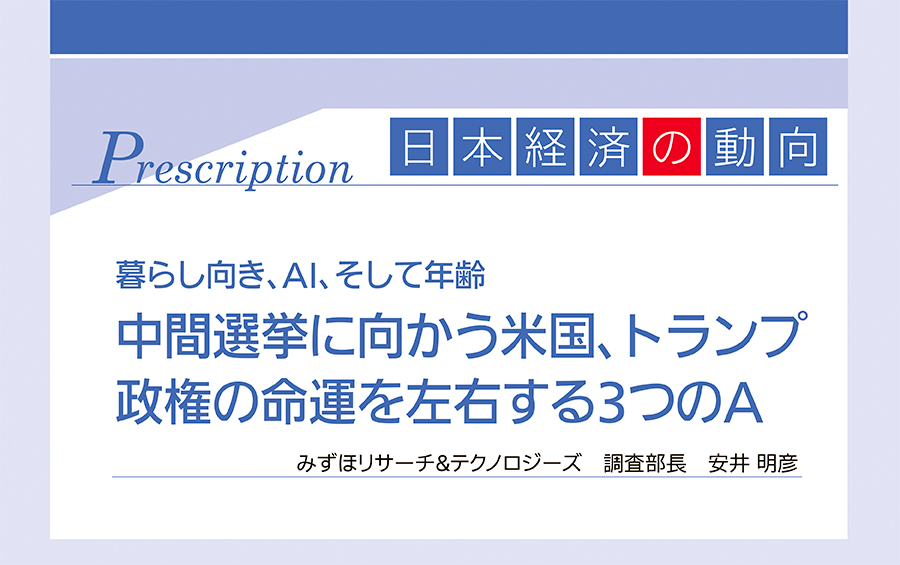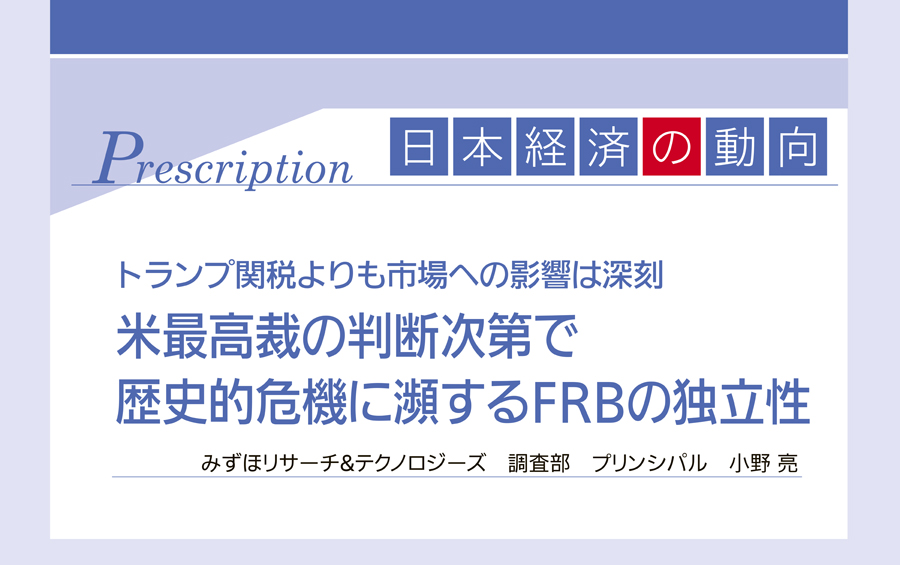日本経済の動向
「トランプ後」も問われる日本経済の中期的な成長力
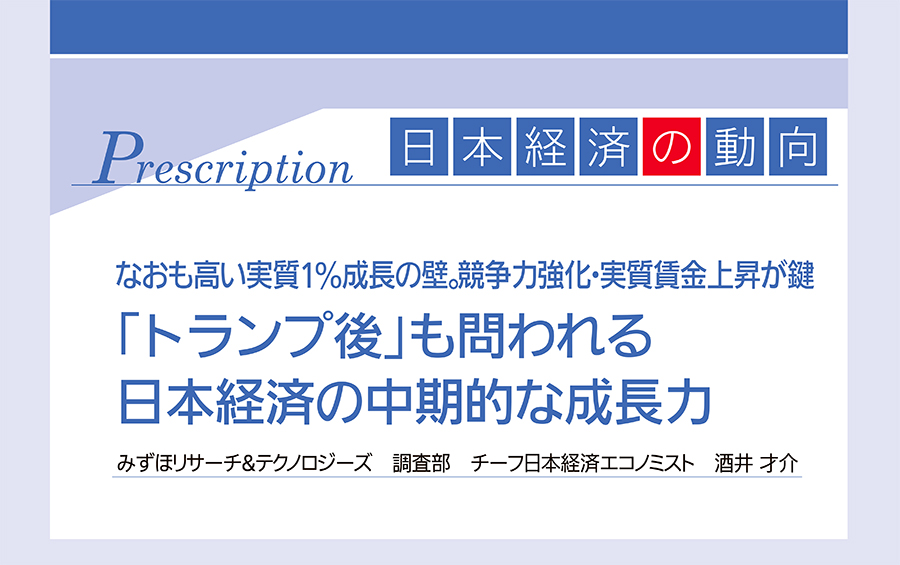
関税を巡る日々の混乱に目を奪われがちだが、日本経済・企業の構造的な「実力」の低迷にも目を向ける必要がある。相対価格の不利が和らいでも、実力が伸びなければ『トランプ後』の中期成長を楽観視することはできない。そこで今回は、輸出や個人消費の中期的な動向に着目し、トレンドとしての日本経済の成長力と課題について考察する。
世界市場における日本のプレゼンスは低下
中国の競争力向上に伴う輸出シェアの拡大等を受けて、日本の輸出はトランプ政権が関税を引き上げる前から伸び悩んでいる。中国やアジアが競争力向上に伴い世界市場における輸出シェアを拡大させる一方で、日本の主要輸出品目(自動車や機械関連)のシェアはいずれも低下基調で推移している。
円高や震災・エネルギー不足への懸念、地産地消への対応力向上などを踏まえた日本企業による生産拠点の海外シフトに加え、中国企業の台頭による価格競争力低下が背景にあると考えられる。「製造強国」に向けてまい進する中国の存在感は今後さらに増していく可能性が大きく、世界における日本主要産業のプレゼンスを維持するためには、中国に匹敵するような競争力のある分野の見極め・強化が不可欠であろう。
実質所得の低迷で個人消費は伸び悩みが継続
加えて、実質賃金の低迷に伴う個人消費の伸び悩みが継続しており、近年は高水準の賃上げが実現する中にあっても足元の個人消費の水準は依然としてコロナ禍前(2019年平均)の水準程度にとどまっている。過去20年の個人消費の伸び悩みの背景には実質所得の伸び悩み(こちらも過去20年の年平均増加率は+0.2%程度)がある。
近年は、人手不足を背景に名目雇用者報酬が高い伸びを示している一方、消費者物価も食料品を中心に高い伸びで上昇していることから、実質可処分所得の改善にはつながっておらず、実質ベースの所得は依然低い伸びにとどまっている。
実質1%成長のハードルは高い
輸出や個人消費といった需要の柱が伸び悩めば、日本経済全体の成長率の上昇も期待しにくい。中期的にみた日本の実質GDP成長率は精々+0%台半ば程度と筆者は見込んでいる。政府は、「経済財政運営と改革の基本方針2025」(骨太の方針)において、「経済・財政・社会保障の持続可能性を確保するためには、生産年齢人口の減少が本格化する中にあっても、中長期的に実質1%を安定的に上回る成長を確保する必要がある」としているが、現状、実質1%成長のハードルは高いと言わざるを得ない状況だ。
こうした状況では、企業の期待成長率も高まらないため、国内への投資も拡大しにくい。日本政策投資銀行「全国設備投資計画調査」(2025年6月)によれば、10年先の海外生産拠点を強化する意向の企業が63%に上る一方、国内生産拠点を強化する意向の企業は49%にとどまっている。地政学リスク・経済安全保障に対する意識が高まる中で、サプライチェーンの見直し・生産拠点の分散の一環として国内に投資をする動きは出ているものの、輸出・個人消費を中心とした需要の低迷で能力増強投資に踏み切りにくい上、人手不足・電力不足等の供給制約も相まって、中期的にみた国内の投資気運が盛り上がっているとは言い難い。
中期的な競争力強化・実質賃金上昇が鍵
日本経済の持続的成長に向けて、企業の競争力・生産性の向上と、家計の所得向上を通じた内需の底上げが鍵になると考えられる。政府としては、研究開発・イノベーションへの支援を通じて日本経済の競争力・「稼ぐ力」を向上させると同時に、労働生産性の向上等を通じて、インフレを上回る水準での持続的な賃上げを促進し、消費需要を拡大させる必要があるだろう。電気自動車、人工知能、再生エネルギー関連など、グローバルな成長分野における日本のプレゼンスは低く、競争力の再強化に向けて官民を挙げた巻き返しが必要だ。
一方で、米国第一主義(米国の孤立化)、「製造強国」「自立自強」にまい進する中国の台頭といった国際的な潮流は変わらない点を踏まえると、輸出(とりわけ米国向け)で稼ぐビジネスモデルだけでは日本経済の持続的な成長の実現が難しいと考えられ、内需で稼ぐモデルとの両立が鍵になるだろう。「企業の競争力向上・生産性上昇」と「家計の所得・消費の増加」の好循環を実現させられるかどうかに、中期的な日本経済の成長実現がかかっている。
【冊子PDFはこちら】