特集
「複合災害」から国土を守る建設業の役割とは
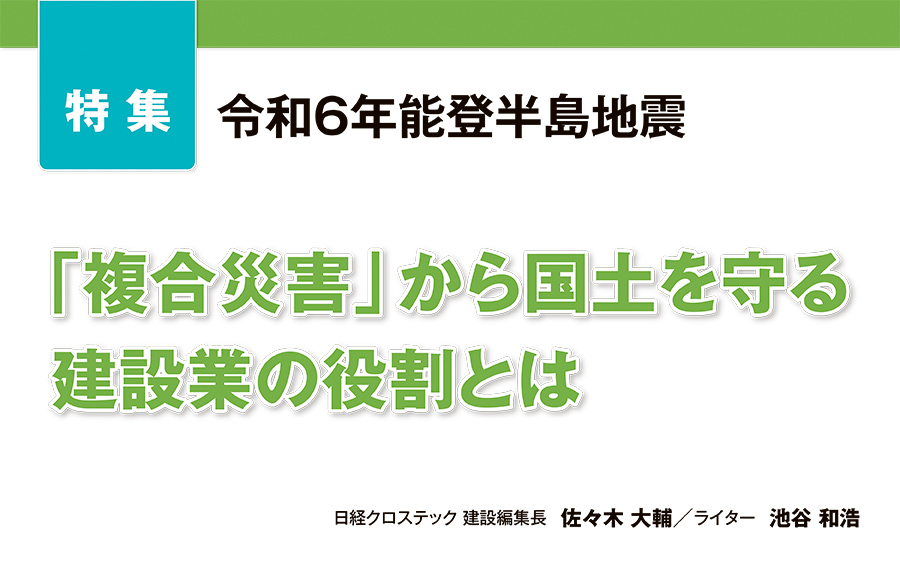
最大震度7を観測した令和6年能登半島地震。被災地では今も復旧・復興工事が続いています。2024年の1月1日、つまり元日に本震が発生したこの地震は、日本が地震多発国であることを痛感させる大災害となりました。被災地における建設会社の奮闘を振り返るとともに、将来像を考えます。

■ 石川県輪島市内での道路啓開作業の様子。2024年1月6日撮影 (写真:日経クロステック)
令和6年能登半島地震は2024年1月1日午後4時10分ごろに発生しました。震源は能登半島の北東に位置する石川県珠洲市。地震の規模を示すマグニチュードは7.6でした。有名な観光地でもある輪島市ほかで震度7を観測しました。
この地震は近年まれに見る「複合災害」となりました。まずどのような災害だったのかを見ていきます。
能登半島を地図で見ると、日本列島から北東方向に向け、日本海へくの字状に突き出たような形状をしています。震源はそうした半島の先端でした。強い揺れにより津波が発生、気象庁によると、能登町では津波の浸水した高さが4.7mに達しました。
気象庁が大津波警報を発令する中、輪島市沿岸部で火災が発生しました。消防隊は海や川の河口付近から取水できず、十分な消火活動を行えませんでした。このため最終的に、約240棟もの住宅・建築物が焼損する大火事となりました。
強い揺れで数多くの住宅・建築物が倒壊。裏山の土砂崩れなども頻発。「直接死」だけでも200人以上の人が亡くなりました。また住まいを失い、3万人以上が一時避難を余儀なくされました。
能登半島は山地が多く、主要幹線道路は谷あいを縫い、海岸に沿う形で走っていました。特に奥能登地域と呼ばれる珠洲市、輪島市、能登町、穴水町などでは、斜面崩落、トンネルの大規模崩落などにより、この道路が各地で寸断しました。いくつもの集落が孤立し、救助・避難活動や物資支援は困難を極めました。
沿岸部では地震で地盤が隆起し、例えば輪島港では船が出られなくなりました。防潮堤や岸壁も大きく破損しました。能登空港も滑走路に亀裂や段差が発生。ターミナルビルも被災し、空の便も寸断しました。
震源からやや離れた位置でも、地盤の液状化現象が多発しました。建物が大きく不同沈下したほか、地盤表層が側方流動を起こし、建物ごと流れて動いてしまいました。






